「勉強だけでなく、生きる力も身につけてほしい」という思いがあるパパさんやママさんも多いのではないでしょうか。近年注目されている「非認知能力」は、自己肯定感や協調性、やり抜く力など、テストでは測れないものの、将来に深く影響する力の1つです。
本記事では、非認知能力を鍛える遊びや高めるメリットをご紹介します。また、非認知能力を鍛える遊びの効果を上げるためのポイントも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

非認知能力を幼児期に伸ばしたいといわれる理由とは?

幼児期は脳が著しく成長する大切な時期であり、日々の経験や関わりを通じて子どもの内面的な力が育まれます。この時期に育てられる非認知能力は、学力や知識だけでは測れない「生きる力」の基盤の1つです。
たとえば、物事に粘り強く取り組む姿勢や、他者と協調する態度、感情を適切にコントロールする力などがあげられます。これらの力は将来の社会生活でも役立ち、自信を持って人生を歩むための土台となっていきます。
GENI公式オンラインショップ by エドインター ![]() では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター ![]()
子どもの非認知能力を高めるメリットは3つ

次は、子どもの非認知能力を高めるメリットについて解説します。
- 協調性やコミュニケーション能力が育める
- 理性的に行動する力が身につけられる
- 習い事や学習の意欲が高まる
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
協調性やコミュニケーション能力が育める
非認知能力は、他者と良好な関係を築くためには欠かせない能力です。集団のなかでの遊びや日常のやりとりを通じて、子どもは自分の気持ちを表現する力や、相手の気持ちに気づく感受性を自然と身につけていきます。
友だちと一緒に遊ぶことにより、順番を守る、譲り合う、助け合うなどの行動が身につき、協調性やコミュニケーション能力が伸びていきます。
理性的に行動する力が身につけられる
子どもが自由に遊んだり生活したりするなかで、先を見通して行動する力や、状況に応じた判断をする力が少しずつ育まれていきます。たとえば、「次に何をすればいいか」「どこでどのようなふるまいが必要か」を考えることは、予測力や計画性の基礎となります。
また、感情に流されずに我慢したり、時間や空間を意識して行動したりすると、自制心や忍耐力も自然と身につくケースが多いです。これらは、集団生活を円滑に進めるために欠かせない力となります。
習い事や学習の意欲が高まる
子どもが遊びや日常生活のなかで目標に向かって挑戦する経験は、集中力や計画性、粘り強さを育む機会です。自分で決めたことをやり遂げる過程で、「もっと上手にできるようになりたい」という向上心が芽生え、学習への意欲にもつながっていきます。
失敗を経験しながらも試行錯誤を重ねれば、問題解決力も養われます。こうした非認知能力は、就学後の学びや社会生活を力強く支える基礎となるに違いありません。
GENI公式オンラインショップ by エドインター ![]() では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター ![]()
なお、子どもに人気の習い事については、こちらの記事で詳しく解説しています。
子どもの非認知能力を鍛える遊び15選

次は、子どもの非認知能力を鍛える遊びについてご紹介します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
工作
工作は、子どもが自由な発想で取り組める遊びの1つであり、創造力や集中力を自然と育めます。使う素材は特別なものでなくても、空き箱やペットボトル、紙の端材など身近なもので構いません。
自分の手で形にしていくなかで、子どもは試行錯誤を繰り返しながら工夫する力を身につけていきます。また、黙々と作業することで集中する力も高まり、完成したときの達成感が自己肯定感にもつながります。
お絵描き
お絵描きは、子どもが自分の感じたことや思いついたことを自由に表現できる貴重な活動です。何を描くかを自分で決め、好きな色や形を選ぶことで、創造力や自己表現の力が自然と育まれていきます。
また、道具を握って描く動作は、手先の器用さや力加減の調整にもつながります。大人が手を加えすぎず、子どもが主体的に楽しめるように環境を整えてあげましょう。これにより、表現への意欲がさらに高まり、非認知能力の発達にもよい影響を与えます。
料理・お菓子作り
料理やお菓子作りは、子どもの考える力や工夫する力を育てる絶好の機会です。材料の準備から手順の確認、仕上がりのイメージまで、自分なりに段取りを考える過程で、論理的な思考力や問題解決力が養われます。
また、家族や友だちと一緒に作業すれば、協調性や相手を思いやる心も育まれやすいです。難しい作業でなくても、簡単な調理体験を通じて、「自分にもできた」という達成感が自信につながり、非認知能力の向上が期待できます。
絵本の読み聞かせ
絵本の読み聞かせは、子どもの心にさまざまな刺激を与え、豊かな感性を育てる大切な時間です。物語の展開を想像したり、登場人物の気持ちに寄り添ったりすると、想像力や共感力が自然と育まれていきます。
また、読み手との対話を通じて、自分の感じたことや考えたことを言葉で表現する力も養われます。絵本の時間を親子のふれあいの場として、子どもが物語の世界に浸れる環境づくりが大切です。
読書
読書は、子どもの内面を豊かにして、多様な非認知能力を育む活動の1つです。物語の登場人物に感情移入することで共感力が育ち、さまざまな出来事や価値観に触れることで思考力や倫理観が深まります。
また、子ども自身が「読んでみたい」と感じる本に出会うことが大切です。好きな本を自由に選べる環境を整えると、読書は習慣となり、自己肯定感や向上心も自然と育っていきます。
ごっこ遊び
ごっこ遊びは、子どもが身近な出来事や人物を模倣しながら、自分の考えを表現する大切な遊びです。店員や医者、ヒーローなどになりきると、想像力が育まれ、場面に応じた言葉のやりとりを通じてコミュニケーション能力も高まります。
また、友だちと役割を分担して遊べば、協調性が自然と身につきやすいです。大人も一緒に参加して、子どもの発想を尊重してあげると、遊びの世界はさらに広がり、非認知能力の成長につながります。
おもちゃ遊び
おもちゃ遊びは、子どもの創造力や集中力を育てる大切な時間です。積み木やブロック、パズルのように自由に形を変えられるおもちゃは、試行錯誤しながら遊べるため、工夫する力や観察力も自然と育まれやすいです。
子ども自身が興味を持ったおもちゃを選び、思う存分遊べる環境を整えれば、遊びへの意欲が高まり、非認知能力の向上につながります。また、専用の遊びスペースを設けると、より集中して取り組めるようになります。
なお、積み木は何歳から何歳まで遊べるのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
共通点探し
共通点探しは、子どもが物事の特徴を捉え、分類する力を育む知的な遊びです。最初は「犬と猫=動物」のような分かりやすい組み合わせからはじめると、子どもも楽しみながら取り組めます。
慣れてきたら、「自転車とカメラ」など一見関係のなさそうなものを使い、「動く部分がある」といった共通点を見つける挑戦に進んでみましょう。こうした活動は、考える力や発想力を鍛えるだけでなく、自分の気づきを言葉で表現する力も育ててくれます。
音楽遊び
音楽遊びは、子どもの感性を刺激して、さまざまな非認知能力の育成に役立ちます。自分で音を出す体験を通じて、表現力や創造力、リズム感が自然と育まれていきます。
たとえば、タンバリンやカスタネットのように、手を使って音を鳴らせる楽器は、能動的な関わりを促すのに最適です。また、子どもが興味を持つ音楽を取り入れると、集中力や意欲も高まり、楽しみながら取り組める環境が整います。
なお、リトミックの効果については、こちらの記事で詳しく解説しています。
鬼ごっこ
鬼ごっこは、子ども同士が関わり合いながら楽しむなかで、自然と非認知能力が育つ遊びです。逃げる側も追う側も、相手の動きを読みながら素早く判断して、どう動くかを考える必要があるため、判断力や思考力が養われます。
また、仲間との連携やルールを守ることを通じて、協調性やコミュニケーション能力も育まれやすいです。体を動かしながら遊べるため、心身の発達にもつながり、健やかな成長を促す効果が期待できます。
ボール遊び
ボール遊びは、子どもが自由に体を動かしながらさまざまな力を育てられる遊びです。投げる、蹴る、受け取るといった動作を通じて運動能力が高まるだけでなく、遊び方を工夫するなかで想像力や判断力も養われます。
また、ほかの子どもや大人と一緒に遊ぶと、ルールを守る姿勢や相手とのやり取りを学び、協調性やコミュニケーション力も育まれます。外でのびのびと行うボール遊びは、体力作りにも効果的です。
水遊び
水遊びは、子どもが自然と関わりながら感性を育てる絶好の機会です。水をすくったり流したりするなかで、手触りや音、温度の違いに気づき、五感が刺激されます。
また、水でどのように遊ぶかを自分で考えたり、環境に応じて遊び方を工夫したりするため、想像力や発想力が広がります。さらに、天候や季節に合わせて、屋外やお風呂場などさまざまな場面で取り入れられるため、遊びの幅が広がる点も魅力です。
泥遊び
泥遊びは、自然のなかで自由に発想を広げられる遊びの1つです。水分の加減によって形や感触が変わる泥は、山や川を作ったり型を取ったりと、遊びのバリエーションが豊富です。
水分や土の量を調整して遊ぶため、子どもは自分なりの工夫を重ねて、思考力や創造力を育てていきます。また、どのように形にするかを考えるなかで、計画性や応用力も養われます。
自然体験
自然とのふれあいは、季節によって変わる風景や草花の変化に気づけるため、観察力や探求心が育まれます。葉っぱの形や色、石の手触りなど、五感を使って自然に触れることは、子どもの感性を豊かにする貴重な体験です。
また、近所の公園や道端でも十分に自然を感じられる環境はあり、特別な準備をしなくても楽しめます。自然のなかでの遊びを通じて、想像力や感情の動きも大きく育っていきます。
虫とり
虫とりは、子どもの興味や観察力を引き出す自然遊びの1つです。虫の動きや生態をじっくり観察することで、好奇心や探究心が育ちます。
また、虫を追いかけたり捕まえたりするなかで、生き物に対する思いやりや命の尊さを学ぶ機会にもなります。身近な場所でできる活動ながら、多くの学びが詰まっており、自然とのふれあいを通して感性や心の豊かさを育む貴重な体験です。
GENI公式オンラインショップ by エドインター ![]() では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター ![]()
なお、遊びが持つ他の知育効果が知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください。
子どもの非認知能力を鍛える遊びの効果を上げるポイントは7つ

次は、子どもの非認知能力を鍛える遊びの効果を上げるポイントについて解説します。
- 子どもの好奇心や関心を尊重する
- 知らない子どもと遊ぶ機会を積極的につくる
- 保護者が子どもの手本になる
- 安全に遊べる環境を用意する
- ありのままを受け入れてあげる
- 子どもが興味をもつ遊びを提供する
- 感情的な行動を抑えられるようにする
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
子どもの好奇心や関心を尊重する
子どもの成長には、自分で選んで行動する経験が欠かせません。遊びや学びのなかで「何をするか」「どうするか」を自分で考えることで、主体性や思考力が自然と育まれていきます。
大人が一方的に指示するのではなく、子どもが興味を持ったことに取り組めるような環境を整えることが大切です。選択する体験が積み重なると、自信や意欲が芽生え、想像力や探求心といった非認知能力も大きく伸びていきます。
知らない子どもと遊ぶ機会を積極的につくる
子どもが他者と関わる経験は、社会性やコミュニケーション能力を育むためには欠かせない活動の1つです。友だちと一緒に遊ぶなかで、ルールを守ったり、相手の気持ちを考えたりする大切さを学びます。
ときには思い通りにいかない場合もありますが、このような体験を通じて、協調性や自己をコントロールする力が育まれます。他者とのやりとりを重ねて、非認知能力のひとつである社会的スキルが自然と身についていきやすいです。
保護者が子どもの手本になる
子どもは日々の生活のなかで、大人の言動をよく観察して多くのことを学んでおり、非認知能力も例外ではありません。身近な大人のふるまいが、子どもの成長に大きな影響を与えています。
たとえば、落ち着いて話す姿や感情をコントロールする様子、他者への思いやりなどを目にすると、子どもも同じようなふるまいを見せようとします。非認知能力を育てたいと願う場合は、大人自身がお手本となる行動を心がけるようにしましょう。
安全に遊べる環境を用意する
子どもの非認知能力を伸ばすためには、自由に遊べる環境を整えてあげてください。好きなことに夢中になって遊ぶことにより、想像力や集中力が養われますが、安心して過ごせる空間がある場合は、その効果が高まります。
遊びに集中できるように、危険な物は事前に取り除き、安全性に配慮したスペースを用意しましょう。たとえば、キッズテントやプレイマットを活用すれば、自分だけの落ち着いた空間ができ、子どもは自由に遊べます。
ありのままを受け入れてあげる
子どもの非認知能力を育むには、日々の関わりのなかで自己肯定感を育てる必要があります。子どもが失敗したときや間違った行動をしたときでも、行動だけに目を向け、存在そのものを否定しないようにしましょう。
「どうすればもっとよくできたかな?」と問いかけると、子どもは自分で考える力や問題解決力を伸ばせます。褒めることと注意のバランスを取りながら、安心して挑戦できる環境を整えてあげることが親の大切な役割です。
子どもが興味をもつ遊びを提供する
子どもの非認知能力を育てるには、自発的に遊びたくなる環境づくりが大切です。子どもが興味を持ちそうな遊びを中心にしながらも、ときには異なるジャンルのおもちゃや遊びをそっと混ぜてみると、新たな関心が芽生えるきっかけになります。
予想外の反応や意外な楽しみ方を見つけると、柔軟な思考力や好奇心の刺激にもつながります。しかし、興味を押しつけるようなことは避け、子ども自身が選び取る機会を尊重してあげましょう。
なお、子どもに人気のマグビルドについては、こちらの記事でご紹介しています。
感情的な行動を抑えられるようにする
遊びのなかで子どもが怒ったり泣いたりするのは、よくある自然な反応です。このような感情の揺れを経験するなかで、子どもは少しずつ自分の気持ちに気づき、それをコントロールする力を育んでいきます。
非認知能力の1つである自己制御力は、すぐに身につくものではありません。保護者が子どもの気持ちに寄り添いながら、「今はどんな気持ち?」と声をかけると、感情を理解して、適切に表現する力を育む手助けができます。
GENI公式オンラインショップ by エドインター ![]() では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター ![]()
まとめ

本記事では、非認知能力を鍛える遊びや高めるメリット、効果を上げるためのポイントをご紹介しました。
非認知能力は、思いやりや粘り強さ、意欲といった「人としての土台」となる力であり、脳が著しく成長する幼児期に育むことが大切です。この時期に非認知能力を伸ばすと、協調性やコミュニケーション能力、感情のコントロール、学びへの意欲といった、将来の土台となる要素を育めます。
工作やお絵描き、絵本、ごっこ遊び、おもちゃ遊びなど、さまざまな遊びを通じて、子どもの好奇心を刺激できれば、非認知能力が高められます。遊びの効果を高めるためには、親が寄り添いながら、子どもの関心や感情に目を向けることが大切です。
GENI公式オンラインショップ by エドインター ![]() では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
では、非認知能力の向上におすすめな木製知育玩具を販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安心です。また、積み木やおままごと、パズルなど、おもちゃの種類も豊富です。
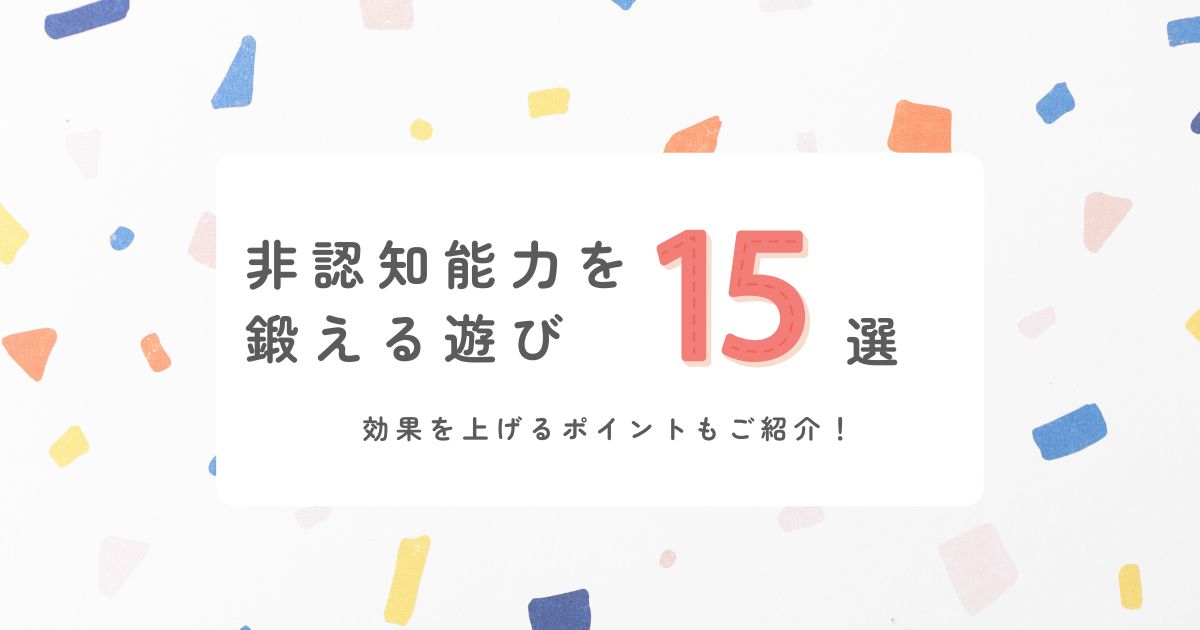



-27-150x150.jpg)
-48-150x150.jpg)

