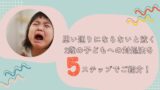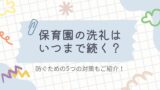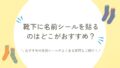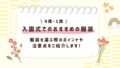乳児期は0歳から1歳未満、幼児期は1歳〜6歳までとされているのが一般的です。しかし、育児や発達の観点ではさまざまな考え方があり、期間の定義が異なる場合もあります。
本記事では、乳幼児期とはいつ(何歳)までか、期間の定義、育児のポイントをご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
乳幼児期とはいつ(何歳)まで?
まず、乳幼児期とはいつ(何歳)までについて解説します。
- 「乳児」と呼ばれる期間の定義
- 「幼児」と呼ばれる期間の定義
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
「乳児」と呼ばれる期間の定義
乳児とは、児童福祉法や母子健康法によると、生後から1歳の誕生日を迎える前日までと定義されています。生まれたばかりの赤ちゃんが、やがて首が据わり、寝返りを打ち、立ち上がろうとするようになる時期です。
さらに、母乳やミルクを栄養源としながら、離乳食をはじめる時期でもあり、食事を通じて新たな味や感触を学びます。また、乳児期には簡単な言葉を発するようになる子どももおり、周囲とのコミュニケーションが芽生える大切な時期です。
「幼児」と呼ばれる期間の定義
幼児とは、児童福祉法では、1歳の誕生日を迎えたあとから小学校入学前までの子どもと定義されています。この時期は、身体的にも精神的にも大きな成長を遂げる大切な期間です。
たとえば、言葉の発達が著しく、単語を話しはじめるだけでなく、簡単な文章で自分の気持ちを伝えられるようになる子どももいます。また、歩行が安定して、自分で走り回ったり遊びに挑戦したりすることで運動能力が向上します。
この成長のなかでは、排せつの自立や社会性の発達など、保護者や周囲のサポートが欠かせません。それぞれの成長速度は異なるため、一般的な発達目安を参考にしつつも、個々の特性を大切にした接し方が求められる時期です。
乳児期や幼児期にみられる成長
次に、乳児期や幼児期にみられる成長について解説します。
- 乳児期
- 幼児期
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
乳児期
新生児期には、泣いて意思を伝えていた赤ちゃんも、数か月経つと笑顔を見せたり、周囲の人に反応したりするようになります。
また、視覚や聴覚、触覚などの感覚も発達して、周囲の環境に興味を持ちはじめます。運動面では、首が据わり、寝返りやお座りができるようになり、ハイハイやつかまり立ちへと進んでいく時期です。
食事面では、母乳やミルクを主な栄養源としていた赤ちゃんが、成長とともに離乳食を取り入れ、徐々に食事からの栄養摂取へ移行していきます。このような変化を支える周囲の関わりが、赤ちゃんの健やかな成長を促します。
幼児期
1歳を迎えると、子どもは行動範囲が広がり、自分の意思を表現するようになります。歩けるようになると、自分の興味のあるものに近づく機会が増え、探求心が芽生えます。言葉も少しずつ発するようになり、大人の話す内容を理解しはじめるのが特徴です。
また、自己主張が強くなり、思い通りにならないと泣いたり怒ったりする場合もありますが、これも成長の一環です。また、2歳頃になると二語文を話す子も増え、簡単な会話ができるようになります。
同時に、自分でできることが増え、自立しようとする姿が見られる時期です。さらに、3歳に近づくとほかの子どもと関わるのが楽しくなり、友だちとの遊びを通じて協調性が育まれます。この時期は、子どもがさまざまな経験を通じて心身の成長を遂げる大切な時期です。
なお、思い通りにならないと泣く2歳の子どもへの対処法については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
【シーン別】乳幼児の区分
次に、シーン別の乳幼児の区分について解説します。
- 医療機関
- 公共交通機関
- 保育園
- 幼稚園
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
医療機関
一般的には、1歳未満の子どもを乳児、1歳から小学校入学前までを幼児と分類しますが、発達の個人差を考慮して、細かく区分する場合もあります。多くの自治体で「乳幼児医療証」を利用すれば、診察や治療の費用が無料または軽減される制度があり、乳幼児の医療費負担を軽減できます。
助成の内容や負担割合は自治体によって異なるため、具体的な適用条件を確認しましょう。最近では、所得制限を撤廃して、すべての子育て世帯が支援を受けられるようにする動きも広がっています。
公共交通機関
公共交通機関において、乳児や幼児の扱いは規則や事業者によって異なりますが、一般的な基準が設けられています。電車やバスでは、乳児(1歳未満)や幼児(1歳から6歳未満)の運賃は無料とされる場合が多く、大人の膝の上に抱っこして乗車するのが一般的です。
しかし、特急列車や指定席を利用する場合は、乳幼児であっても料金が発生する場合があります。飛行機では、2歳未満の乳児は大人の膝の上で搭乗可能ですが、座席を確保する際には幼児料金が必要です。
また、航空会社によっては乳幼児向けの特別なサービスが提供される場合があり、ベビーベッドやミルクの準備などが可能な場合もあります。それぞれ交通機関の規定を事前に確認しておくと、スムーズな移動ができます。
保育園
保育園では、一般的に0〜2歳を乳児クラス、3歳以上を幼児クラスとして区分するのが一般的です。乳児クラスでは、それぞれの子どもに寄り添ったケアが重視され、授乳やおむつ替え、睡眠のサポートなどが日常の中心となります。
一方、幼児クラスでは、3歳以上の子どもが集まり、より自主性や社会性を伸ばす活動が増えます。たとえば、製作や運動遊び、集団でのルールを学ぶ遊びなど、子ども同士の関わりを通じて協調性や創造力を育てる場が設けられる点が特徴です。
乳児クラスと幼児クラスでは、保育内容や保育士の関わり方が大きく異なりますが、どちらも子どもの成長に合わせた配慮がされています。
なお、保育園の洗礼について知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください。
幼稚園
幼稚園に通えるのは、基本的に満3歳以上の子どもであるため、幼稚園に入園する子どもたちは、全員が「幼児」として分類されます。年少クラスには、3歳~4歳になる子どもが在籍するのが一般的ですが、入園のタイミングは園ごとに異なるため、事前に確認しましょう。
また、幼稚園は「学校」として、教育を目的としたカリキュラムが組まれており、保育園のように養護や預かりを主とする施設とは異なる役割を果たします。このため、幼稚園では学習や社会性を育む活動が多く取り入れられています。
入園を検討する際には、教育方針やカリキュラム内容を確認して、子どもに合った環境の選択が大切です。
乳幼児期の育児のポイント
乳幼児期などの心身の発達が著しい時期には、保護者との関わりが子どもの成長に影響を与えます。たとえば、スキンシップを取ったり、日常的にたくさん話しかけたりすると、安心感や信頼感が育まれやすいです。
また、年齢に応じたしつけを行うと、自立心や社会性を養う土台作りができます。この時期に形成される愛着は、その後の人間関係にも影響を与えるため、親子間のつながりが大切です。
さらに、遊びや絵本の読み聞かせなどを通じて、子どもとのコミュニケーションを深めるのもおすすめです。興味を引き出す活動や学びの機会を提供すると、子どもの好奇心や成長を促す環境を整えられます。
なお、絵本の読み聞かせの効果について知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。
乳幼児期 いつ(何歳)まででよくある5つの質問
最後に、乳幼児期 いつ(何歳)まででよくある質問について紹介します。
- 質問1.赤ちゃんとはいつまで?
- 質問2.乳児から幼児になったと感じる瞬間は?
- 質問3.新生児とは?
- 質問4.小児とは?
- 質問5.幼少期とは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.赤ちゃんとはいつまで?
「赤ちゃん」という言葉は専門用語ではなく、日常的に広く使われる呼び名です。一般的には、生まれて間もない子どもを指しますが、その期間に明確な定義はありません。
新生児と呼ばれる出生から28日以内の赤ちゃんや、母乳やミルクを必要とする乳児期の子どもが主に「赤ちゃん」としてイメージされますが、歩きはじめた子どもを赤ちゃんと呼ぶ場合が多いです。この言葉の由来は、生まれたばかりの子どもの肌が赤みを帯びているためと言われています。
また、「赤子」や「赤ん坊」といった呼び方も同じ意味合いで用いられます。「赤ちゃん」は、その時期や特徴に限定されない柔軟な呼び名であり、多くの人に親しまれている表現です。
質問2.乳児から幼児になったと感じる瞬間は?
赤ちゃんから子どもへ成長を感じる瞬間は、日常のなかでふと訪れます。たとえば、ベビーカーや抱っこ紐を卒業したり、自分で歩いて移動したりするようになると、子どもの成長を実感しやすいです。
また、子どもが親のそばを離れ、自分の興味のある遊びに没頭しはじめると、親から少しずつ自立していると気づく場面もあります。さらに、自分の意思を表現したり、簡単な会話ができるようになったりすると、乳児期の終わりを感じる親は多いようです。
これらの瞬間は、成長の喜びとともに、赤ちゃん時代が終わる寂しさを感じさせる、大切な思い出の1ページになります。
質問3.新生児とは?
新生児とは、出生後28日未満の赤ちゃんを指す言葉です。この期間は「新生児期」と呼ばれ、赤ちゃんが外の世界に適応するための大切な時期です。数え方は、誕生日を0日目とする方法が一般的ですが、伝統行事では誕生日を1日目として計算する場合もあります。
新生児期が過ぎると「乳児」として扱われるようになり、さらに成長が進むと「幼児」と呼ばれる時期になります。
質問4.小児とは?
「小児」という言葉は、主に医療や看護の分野で使われ、新生児から思春期までの子ども指す言葉です。思春期の年齢には個人差があり、女児ではおおむね14~15歳、男児では16〜17歳とされています。
一方で、公共交通機関や航空機の運賃制度における「小児」は、6歳〜12歳未満の子どもを指すのが一般的です。同じような年齢層を指す言葉として「児童」や「学童」がありますが、小学生を対象に使われる表現です。
小児という言葉は、文脈によって意味が異なるため、使用される場面ごとに正しく理解する必要があります。
質問5.幼少期とは?
「幼少期」という言葉には、具体的な年齢の定義は存在せず、一般的には「幼い子どもの時期」を指します。このため、どの年齢を幼少期と捉えるかは人によって異なります。
多くの場合、幼児期や学童期を含む1歳〜12歳くらいの期間をイメージする場合が多いですが、あくまで目安に過ぎません。特定の年齢や時期を明確に伝える必要がある場面では、「幼少期」という表現だけではなく、具体的な年齢や区分を補足するのが適切です。
このように、「幼少期」は幅広い年齢層を指す言葉として、状況や文脈に応じて柔軟に用いられています。
まとめ
乳児とは、児童福祉法や母子健康法によると、生後から1歳の誕生日を迎える前日までと定義されています。この時期は、視覚や聴覚、触覚などの感覚が急速に発達して、運動面や食事面などで毎月の変化が目に見えてわかるのが特徴です。
一方、幼児とは、児童福祉法では、1歳の誕生日を迎えたあとから小学校入学前までの子どもと定義されています。この時期は、自分で歩けるようになり、言葉の発達が著しく、自分の意思を表現するため、自己主張が強くなります。
なお、医療機関や公共交通機関、保育園・幼稚園などの場面ごとに「乳幼児」の定義は異なるため、状況に応じた対応が必要です。
乳幼児期は、心身の発達が著しい時期には、保護者との関わりが子どもの成長に影響を与えます。たとえば、スキンシップを取ったり、たくさん話しかけたりすると、安心感や信頼感が育まれやすいです。
この時期に形成される愛着は、その後の人間関係にも大きな影響を与えるため、親子間のつながりが欠かせません。
-7.jpg)