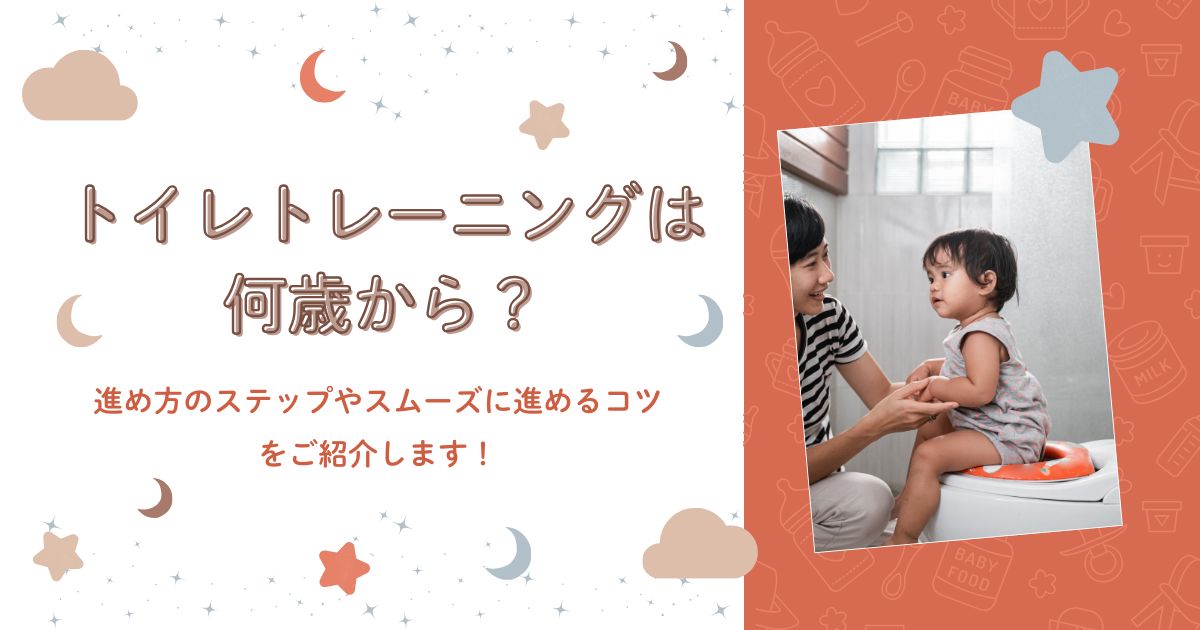トイレトレーニングをいつから始めようか悩まれている方もおられるのではないでしょうか。子どもの成長には個人差があり、開始のタイミングや進め方も異なるため、子ども自身の発達状況を見極めながら進める必要があります。
本記事では、トイレトレーニングは何歳から始めるか、進め方のステップ、スムーズに進めるコツをご紹介します。また、トイレトレーニングに必要なグッズも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
トイレトレーニングは何歳から?

トイレトレーニングを始めるタイミングは、一般的に2歳後半〜3歳頃が目安とされています。この頃に、子どもは少しずつ排泄の感覚を理解して、自分の意思を伝える力も発達してくる時期です。
しかし、成長のスピードには個人差があり、すべての子どもが同じ時期に準備が整うわけではありません。このため、年齢にとらわれず、子ども自身の発達状況を見極めながら進めていきましょう。
トイレトレーニングを始める目安
トイレトレーニングを始める目安は、2歳後半〜3歳頃とされていますが、成長のスピードには個人差があるため、準備が整ったタイミングではじめるようにしましょう。
たとえば、自分でトイレに行こうとする素振りを見せたり、濡れたオムツを嫌がったりする様子が見られると、トレーニングを始めるよいサインとなります。また、大人の声かけに反応できたり、簡単な言葉で気持ちを伝えられたりできるかもポイントです。
トイレトレーニングを始めるのに向いている時期
トイレトレーニングを始める際は、気候も考慮するとスムーズに進めやすくなります。春から夏は、薄着で過ごす場合が多いため、ズボンやパンツの着脱が簡単になり、トイレに行く際の負担が軽減されます。
また、洗濯物が乾きやすい季節でもあるため、よごれてもすぐに洗って対応できる点がメリットです。一方で、秋や冬は厚着になるため、衣服の着脱に時間がかかる場合があります。しかし、子どもの成長や意欲が優先されるべきであるため、最適なタイミングを見極めながら進めましょう。
保育園や幼稚園でのトイレトレーニング

次は、保育園や幼稚園でのトイレトレーニングについて解説します。
- 保育園
- 幼稚園
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
保育園
保育士は、毎年たくさんの子どもたちと関わりながらトイレトレーニングを進めている経験豊富で心強い存在です。保育園でトレーニングを行っている場合は、その方法や進め方を参考にしながら、自宅でも同じリズムで取り組むとスムーズに進みやすくなります。
しかし、すべてを保育園に任せるのではなく、家庭でもトレーニングに励みましょう。たとえば、園でのトイトレの状況をしっかり褒めたり、自宅のトイレを楽しい空間にしたりする工夫をして、子どもが前向きに取り組めるようサポートすることが大切です。
幼稚園
園から事前に練習を促される場合もありますが、焦らず子どものペースを大切にしましょう。3年保育に入る早生まれの子どもは、まだ発達の途中で、トイレトレーニングが完了していない子も珍しくありません。
入園後は、周囲の友だちの影響を受けて、「自分もやってみよう」という気持ちが芽生える場合が多く、徐々に自然とトイレの習慣が身についていきます。
トイレトレーニングの進め方は5ステップ

次は、トイレトレーニングの進め方について解説します。
- ステップ1.トイレを知ってもらう
- ステップ2.便座に座らせてみる
- ステップ3.時間を決めてトイレに誘ってみる
- ステップ4.自分から「トイレ」と言えるようになる
- ステップ5.トレーニングパンツを履いて過ごしてみる
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
ステップ1.トイレを知ってもらう
オムツに慣れている子どもにとって、排泄をトイレでするという概念はまだ理解しづらいものです。このため、絵本や動画、アプリなどを活用して、トイレの役割を伝えてあげましょう。
また、大人がトイレに行く様子を見せると、自然と興味を持ちやすくなります。トイレを身近なものとして認識すれば、子ども自身が「やってみたい」と思えるようになり、トレーニングがスムーズに進みやすくなる場合があります。
ステップ2.便座に座らせてみる
子どもが起きた直後やお昼寝明けなど、膀胱におしっこが溜まっているタイミングで座らせると、成功しやすくなります。最初は、おしっこが出なくても問題ありません。
トイレに座ること自体に慣れさせるのが目的のため、怖がらずに座れるか、落ち着いていられるかを確認しながら進めましょう。また、補助便座やおまるを活用して、安心できる環境を整えてあげるのもおすすめです。子どもが嫌がる場合は無理をせず、少しずつ慣れさせていきましょう。
ステップ3.時間を決めてトイレに誘ってみる
最初のうちは、自分から「おしっこに行きたい」と言えない場合が多いため、大人が声をかけて習慣づけるようにしましょう。たとえば、「朝起きたとき」「食事の前後」「お風呂に入る前」「寝る前」など、決まったタイミングでトイレに誘うと、排泄のリズムをつかみやすくなります。
成功したときは「できたね」としっかり褒めてあげると、トイレに行くことへの自信につながり、次第に自分から伝えられるようになります。
ステップ4.自分から「トイレ」と言えるようになる
トイレトレーニングを進める際は、まず大人が定期的に声をかけ、トイレに座る習慣をつけましょう。生活のなかで「食事の後」や「お昼寝の後」など、一定のタイミングで誘ってみることが大切です。
トイレで成功したら、たくさん褒めると自信につながります。はじめのうちは、タイミングが合わず間に合わない場合もありますが、「教えてくれてありがとう」と声をかけ、前向きな気持ちを持たせてあげましょう。繰り返すうちに、自分から「トイレに行きたい」と伝えられるようになっていきます。
ステップ5.トレーニングパンツを履いて過ごしてみる
トイレでの排泄が少しずつできるようになってきたら、日中の時間帯からトレーニングパンツに切り替えてみましょう。トレーニングパンツは、おむつほどの吸収力がないため、万が一お漏らしをすると「濡れて気持ち悪い」と感じやすくなります。
トイレトレーニングの過程では、失敗もつきものですが、それも大切な学びの一部です。焦らず、失敗しても「大丈夫だよ」と優しく声をかけ、前向きな気持ちで取り組めるようサポートしましょう。
トイレトレーニングをスムーズに進めるコツは5つ

次は、トイレトレーニングをスムーズに進めるコツについて解説します。
- トイレを楽しい場所にする
- ごほうびシールを活用する
- 無理に座らせない
- 絶対に叱らない
- たくさん褒めてあげる
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.トイレを楽しい場所にする
トイレトレーニングを始めたばかりの子どもにとって、トイレは慣れない場所であり、不安を感じるケースもあります。トイレを怖がったり行くのを嫌がったりする場合は、環境を工夫してみましょう。
たとえば、子どもの好きなキャラクターのポスターを貼ったり、お気に入りの絵本を置いたりすると、トイレが楽しい場所だと感じられるようになります。また、明るい照明や温かみのある色の装飾を取り入れるのも効果的です。
このように、トイレへの抵抗感をなくし、「行ってみよう」と思える雰囲気を作ることが大切です。
2.ごほうびシールを活用する
トイレトレーニングを楽しく進めるためには、小さな成功を積み重ねていくことが大切です。子どもは目に見えるごほうびがあるとやる気がアップしやすくなるため、トイトレの導入として、ごほうびを活用してみるのがおすすめです。
たとえば、好きなキャラクターのシールを貼るカレンダーを用意すると、「また頑張ろう」という気持ちにつながります。また、「すごいね!」「がんばったね!」と声をかけながら取り組むと、トイレへの前向きな気持ちが育めます。
3.無理に座らせない
トイレトレーニングでは、進み具合をほかの子と比べずに、それぞれのペースを大切にする必要があります。無理にトイレへ誘ったり、嫌がるのに便座に座らせたりすると、かえってトイレへの抵抗感が生まれてしまいかねません。
まずは、トイレに親しみを持てるよう、楽しい雰囲気を作りながら進めましょう。成功や失敗に一喜一憂せず、子どもが安心してトイレに向かえるように、ゆったりとした気持ちで見守ることが大切です。
4.絶対に叱らない
トイレトレーニングを成功させるために大切なのは、失敗を責めずに見守る姿勢です。子どもは一歩ずつ成長していくものなので、うまくいかなくても焦らず、温かくサポートすることが大切です。
失敗しても励まして、成功したときにはしっかり褒めると、自信につながります。また、ほかの子と比べず、子ども自身のペースを大切にしましょう。リラックスした雰囲気のなかで、「トイレは楽しい」「やってみよう」と思える環境作りが、成功への近道になります。
5.たくさん褒めてあげる
トイレトレーニングが成功したら、しっかり褒めてあげましょう。偶然でもトイレで排泄できたら、「すごいね!」「できたね!」と声をかけたり、ハイタッチをしたりして、子どもが達成感を感じられる工夫が大切です。
この積み重ねが自信につながり、「またやってみよう」「次も頑張ろう」という意欲が生まれます。失敗してしまっても叱るのではなく、前向きな声かけをして、トイレトレーニングを楽しい経験にしていきましょう。
トイレトレーニングに必要なグッズは3つ

次は、トイレトレーニングに必要なグッズについて解説します。
- トレーニングパンツ
- おまるや補助便座
- 踏み台
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.トレーニングパンツ
トレーニングパンツには紙製と布製があり、層の厚さによって種類が分かれています。3層や4層のものは薄手で動きやすく、主に自宅での練習におすすめです。一方、6層のものは吸収力が高く、外出時や保育園での使用に向いています。
また、布製はおしっこの不快感を感じやすく、トイレへ行く意識を促しやすいのが特徴です。紙製は使い捨てができ、忙しいときにも便利です。子どもの成長や生活スタイルに合わせて、場面ごとに最適なタイプを選び、無理なくトイレトレーニングを進めていきましょう。
2.おまるや補助便座
1歳頃から始める場合は、足がしっかりつくおまるを使うと安心感があり、抵抗なく座れます。2〜3歳頃からトレーニングを始めるなら、大人用の便座に取り付ける補助便座を使うのがおすすめです。
補助便座なら、紙で拭く・水を流すなど、トイレの一連の流れも学びやすくなります。また、おまるは排泄物の確認がしやすいメリットがありますが、使用後の後処理が必要です。子どもがリラックスしてトレーニングできるよう、無理なく進めましょう。
3.踏み台
トイレトレーニングを進めるうえで、子どもが安全に便座に座れるようにするためには、踏み台がおすすめです。最初のうちは大人がサポートする場合が多いですが、慣れてくると自分でトイレに行くようになります。
このため、踏み台があると座ったり立ったりの動作がスムーズになり、自信を持ってトイレを使えるようになるため便利です。また、足の裏がしっかり踏み台につくと踏ん張りやすくなり、スムーズな排泄をサポートしてくれます。
トイレの広さに合ったサイズを選び、使いやすい環境を整えましょう。
まとめ

本記事では、トイレトレーニングは何歳から始めるか、進め方のステップ、スムーズに進めるコツ、グッズをご紹介しました。
トイレトレーニングを始めるタイミングは、一般的に2歳後半〜3歳頃が目安とされています。この時期は、少しずつ排泄の感覚を理解して、自分の意思を伝える力も発達してくる時期です。
しかし、成長のスピードには個人差があるため、準備が整ったタイミングではじめることが大切です。たとえば、自分でトイレに行こうとする素振りを見せたり、濡れたオムツを嫌がったりする様子が見られると、トレーニングを始めるよいサインとなります。
保育園でトレーニングを行っている場合は、その方法や進め方を参考にしながら、自宅でも同じリズムで取り組むとスムーズに進みやすいです。また、家庭でトイトレを始める際は、まずはトイレに行ったり、便座に座ったりすることから始めてみましょう。
さらに、トイレを楽しい雰囲気にしたり、ごほうびシールを活用したりすれば、スムーズに始めやすくなります。無理に座らせず、失敗しても励ましの言葉をかけ、出来たことを褒めてあげるように心がけてみてください。