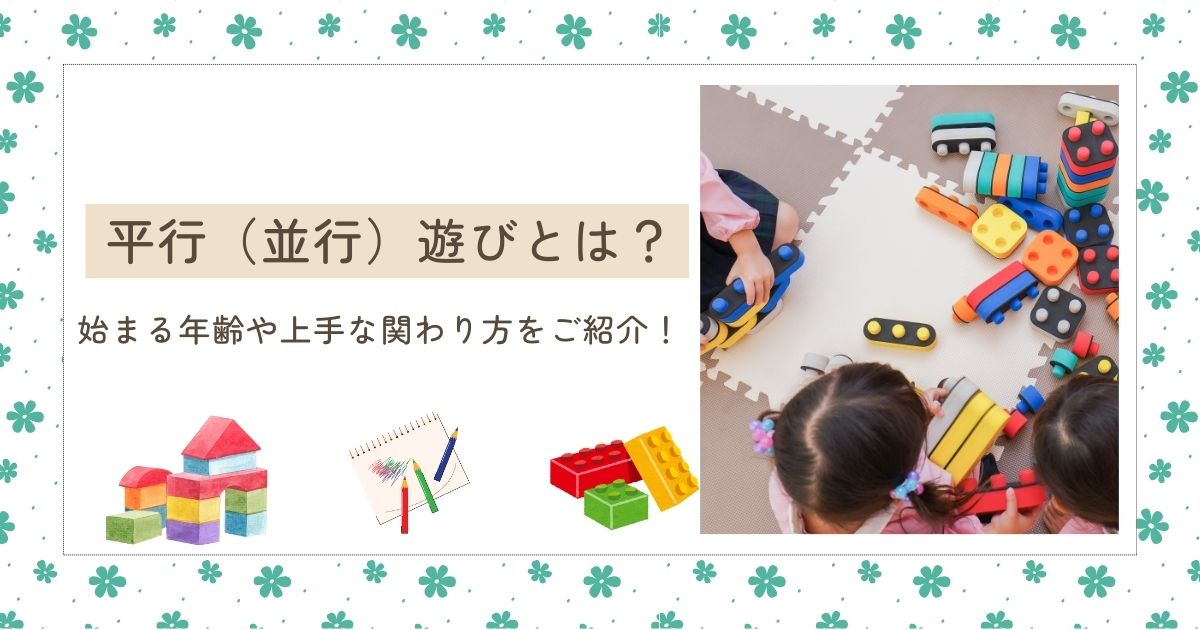保育園や遊び場で子どもの様子を見た際に「友達と遊んでないけど大丈夫かな」と、不安に感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。子どもが隣同士にいながらもそれぞれの世界で遊んでいる「平行遊び」は、一人遊びから集団遊びへ成長するために欠かせないステップの1つです。
本記事では、遊びの発達段階や平行遊びが始まる年齢についてご紹介します。また、平行遊びをしている子どもとの上手な関わり方や遊びの具体例もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
平行(並行)遊びとは?

平行遊びは、子どもたちが同じ空間で似たような遊びをしていても、互いに関わらずにそれぞれの世界で楽しむ遊び方です。たとえば、数人の子どもがブロック遊びをしていても、協力や会話は見られず、自分の遊びに集中しています。
この時期の子どもは、ほかの子を意識していないようでいて、視線を向けたり真似をしたりと、観察を通して学んでいます。このような平行遊びは、発達の途中で見られるごく自然な姿です。
遊びの発達段階
次に、子どもの遊びの発達段階をご紹介します。遊びの発達段階については、以下を参考にしてください。
- 何もしない遊び(0か月~3か月ごろ)
目や耳で観察して刺激を受けている - 一人遊び(0か月~2歳ごろ)
それぞれ好きな遊びを1人で楽しむ - 傍観遊び(2歳ごろ)
ほかの子どもが遊んでいるなかには加わらずに眺めている - 平行遊び(2~3歳ごろ)
近くにいる子と同じ遊びをしていても、互いに交流はなく、自分のペースで遊ぶ - 連合遊び(3~4歳ごろ)
子どもとコミュニケーションを取りながら、同じ遊びをしている。ルールや役割分担はない - 協同遊び(4歳以上)
集団でルールのある遊びができるようになり、遊びのなかでリーダーシップを発揮する子もいる
また、一人遊びについては継続していくのが一般的で、これにより自分の世界を持って楽しめる力が育まれていきます。ただし、遊びの発達には個人差があるため、焦らずに子どもの興味を尊重しましょう。
平行遊びが始まる年齢
平行遊びが始まる年齢としては、3〜4歳ごろが一般的です。しかし、早い子は、1歳半頃から始める場合もあります。
子どもによって発達のタイミングは異なるため、年齢だけで判断せず、どのように周囲と関わっているかを見守ることが大切です。遊びの変化は、成長の一部として温かく受けとめましょう。
平行遊びと一人遊びの違い
一人遊びと平行遊びは似ているように感じられますが、異なる特徴を持っています。一人遊びは、子どもが自分の関心に集中して他者と関わらずに遊ぶ姿です。
一方、平行遊びでは、近くにいるほかの子どもと同じ遊びを選ぶ場合が多く、無意識のうちに「一緒にいる感覚」を味わっている場合があります。コミュニケーションはありませんが、周囲の存在を意識し始める時期の子どもにとって、大切な発達の一環です。
平行遊びが大切な理由
ほかの子の隣で黙々と遊ぶ姿を見て、なぜ一緒に遊ばないのかと不思議に感じる場合もあるかもしれません。しかし、この「平行遊び」は子どもが社会性を育むのに大切なステップの1つです。
「平行遊び」では、周囲の行動を観察したり、まねをしたりして、他者への関心や関わり方を自然に学んでいます。成長に伴い、相手とのコミュニケーションを取る「集団遊び」へと移行するための基礎が、平行遊びによって築かれています。
なお、確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター ![]() では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。
では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。
平行(並行)遊びの具体的な例

次は、平行(並行)遊びの具体的な例について紹介します。
- 積み木でそれぞれが違うものを作る
- おままごとで違うストーリーを展開する
- 友達が走る姿を見て真似して走り回る
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
積み木でそれぞれが違うものを作る
平行遊びの代表例として挙げられるのが、積み木を使用した遊びです。同じテーブルで2人の子どもが遊んでいても、互いの会話はなく、それぞれが自分の世界に没頭しています。タワーや家などを自由な発想で作り上げ、完成すると大人に見せにくる場合もあります。
このように、道具や空間を共有していても、遊びのなかでの直接的な関わりは少なく、隣同士で同じ遊びをしている点が平行遊びの大きな特徴です。こうした時間の積み重ねにより、徐々に周囲の子どもの存在に気づき、意識するようになっていきます。
なお、積み木は何歳から何歳まで遊べるのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:積み木は何歳から何歳まで遊べるの?選び方のポイントもご紹介!
おままごとで違うストーリーを展開する
おままごとは、子どもたちがそれぞれの役になりきって遊ぶなかで、平行遊びが自然に展開される場合の多い遊びです。たとえば、キッチンセットで料理をしている子の隣で、別の子がスーパーの店員になって品出しをしているような場面が見られます。
互いに接点はなくても、同じ空間で遊ぶこと自体が他者への意識を育てる第一歩です。このような経験を通して、子どもは少しずつ他人との距離の取り方を学んでいきます。
友達が走る姿を見て真似して走り回る
平行遊びは、遊具やおもちゃを使用しなくても日常で見られる場合が多いです。たとえば、公園で子どもたちが同じ方向に走っていても、互いに意図は共有しておらず、それぞれの目的で動いています。
具体的には、1人は風で揺れる葉っぱを追いかけ、もう1人はただ体を動かすのを楽しんでいます。見た目には一緒に遊んでいるようでも、実際には関わらずに遊んでいる状態が平行遊びです。
なお、確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター ![]() では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。
では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。
平行(並行)遊びをしている子どもとの上手な関わり方

次は、平行(並行)遊びをしている子どもとの上手な関わり方について紹介します。
- 子どもの遊びにさりげなく参加する
- 友達の存在を意識できるようにする
- 遊びのイメージを尊重する
- おもちゃの取り合いにならないように注意する
- 無理に関わらせようとしない
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
子どもの遊びにさりげなく参加する
平行遊びをしている子どもには、無理に関わりを持たせようとせず、そっと寄り添うことが大切です。子どもが興味を持っている遊びに大人も同じように取り組めば、子どもは自分の行動が受け入れられていると感じて、安心するケースが多いです。
たとえば、ブロックで遊んでいる子の近くで、大人も静かにブロックを組み立てると、自然な関わりが生まれやすくなります。このような積み重ねが、子どもの社会性を育てる一歩となります。
友達の存在を意識できるようにする
平行遊びの時期は、子どもがほかの子の存在に気づきつつも、関わり方がわからない場合が多いです。このような場合に、大人の声かけが周囲への意識を広げる手助けになります。
たとえば、「〇〇ちゃんもすべり台してるね」と伝えると、子どもはほかの子と自分が同じ行動をしていると気づき、共感の芽が育ちます。無理に一緒に遊ばせるのではなく、自然な言葉で橋渡しをするようにしましょう。
遊びのイメージを尊重する
平行遊びの時期には、子ども同士で同じ遊びをしているように見えても、それぞれ異なるイメージで楽しんでいる場合があります。このため、大人が「一緒に遊ぼう」と無理に関係をつくろうとすると、子どもの自然な発想やペースを妨げてしまいかねません。
子どもが自分の世界に集中できるよう見守りながら、少しずつ他者と関わる力を育んでいくことが大切です。このため、遊びの主体が子ども自身である点を意識しておきましょう。
おもちゃの取り合いにならないように注意する
平行遊びの時期には、子どもがほかの子の使っているおもちゃに強く興味を持つ場合があります。しかし、その気持ちをうまく言葉で表現できず、無意識に手を出してしまう場面も少なくありません。
まだ、相手の気持ちを想像するのは難しいため、トラブルを防ぐには遊びの環境づくりが大切です。同じようなおもちゃを複数用意して、子どもが安心して遊びを続けられる工夫が、穏やかな関わり方への一歩となります。
無理に関わらせようとしない
平行遊びの時期には、子どもがほかの子のそばで遊びながらも、自分の世界に集中している様子が見られます。このため、無理に一緒に遊ばせようとする必要はありません。
子どもにとっては、自分のペースで遊びに没頭できることが安心感につながっています。大人はそっと見守りつつ、子ども同士の自然なやりとりが生まれるまで待つようにしましょう。少しずつほかの子の行動に目を向けはじめたら、関わりが芽生えているサインです。
なお、確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター ![]() では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。
では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。
平行(並行)遊びにおすすめのおもちゃ3選

次は、平行(並行)遊びにおすすめのおもちゃについて紹介します。
- 積み木
- ブロック
- お絵かきセット
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
積み木
積み木遊びは、子どもが自分のペースで自由に形を作ったり並べたりできるため、平行遊びの時期におすすめの遊び方です。同じ場所で遊んでいるほかの子どもの作ったものが自然と視界に入り、興味や関心が芽生えるきっかけにもなります。
また、色彩が豊かな積み木や手触りのよい素材を使うと、より遊びが広がります。大人が一緒に遊ぶことにより、子どもは安心して、他者との関わり方への一歩を踏み出しやすいです。
ブロック
ブロックやレゴは、子どもが自分のペースで遊びを楽しめるおもちゃとして、平行遊びの場面によく使用されています。形を組み立てる工程は、集中力や発想力を引き出して、遊びながら自然に学びが深まります。
近くで別々の作品を作っているだけでも、周囲への意識が芽生えやすく、隣の子の作品に興味を持つ場合も多いです。このような遊びは、模倣や共感といった社会的なスキルの発達にもつながる大切な時間となります。
お絵かきセット
お絵かきは、子どもが自分の思いを自由に形にできる遊びであるため、平行遊びにも最適です。たとえば、同じテーブルでそれぞれが紙に向かって黙々と絵を描いていると、自然に隣の子の動きや作品に視線が向く場合が多いです。
このため、会話がなくても、同じ空間で過ごせば、他者への関心を育てるきっかけになります。表現活動は、子どもにとって自分の世界を広げながら、ほかの子の存在に気づいて、自然な交流が生まれる土台にもなっていきます。
なお、確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター ![]() では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。
では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。
まとめ

本記事では、平行(並行)遊びの概要や始まる年齢、上手な関わり方、遊びの具体例をご紹介しました。
平行(並行)遊びは、子どもが一人遊びから集団遊びへと移行する中間の段階であり、社会性や他者への関心を育てる大切な時期です。この遊びは、個人差はあるものの、2〜3歳頃からはじまり、隣で遊ぶほかの子どもに刺激を受けながら成長していきます。
また、この時期は無理にほかの子に関わらせようとせず、遊びの世界を尊重する姿勢が大切です。積み木やブロック、お絵かきセットなど、子どもが自分のペースで自由に遊べるおもちゃを用意して、安心して遊べる環境を整えていきましょう。
なお、確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター ![]() では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。
では、平行遊びの時期におすすめの知育玩具を多数販売しています。厳しい品質基準をクリアしているため、子どもが触れても安全です。また、積み木の種類も20種類以上あり、優しい色合いやデザインも魅力的です。