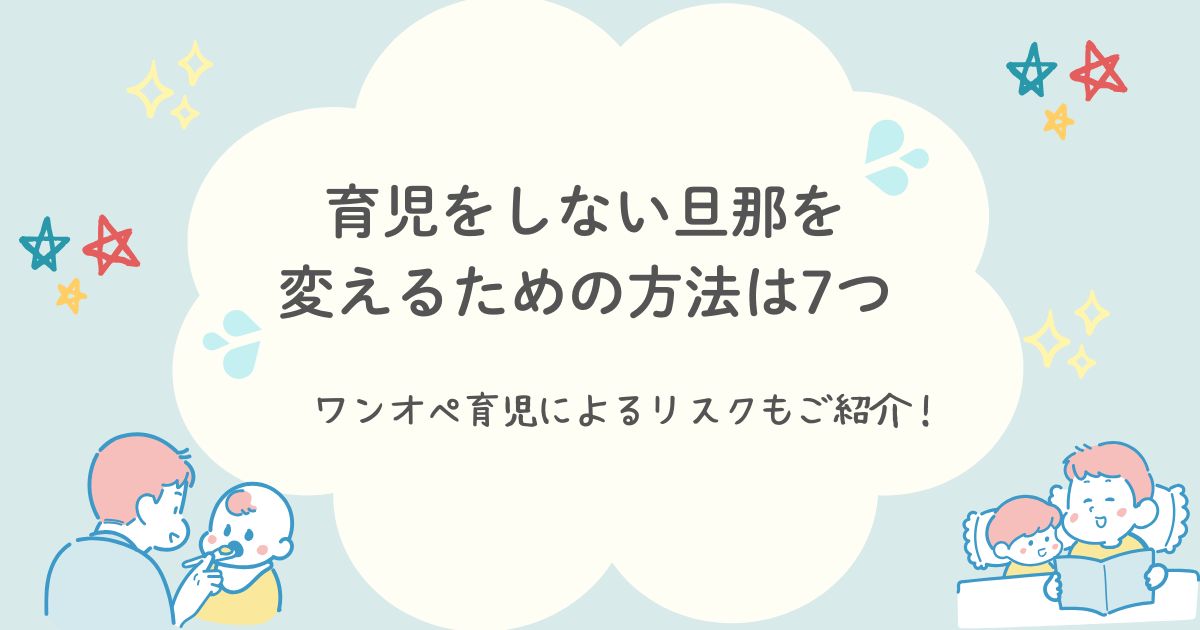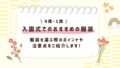育児中のママさんで、パパにも育児に積極的に関わってほしいと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。育児に消極的なパパには共通する特徴があり、ママさんの接し方によって、積極的に動いてくれるようになる可能性があります。
本記事では、育児をしない旦那の特徴や育児をしない旦那を変えるための方法について解説します。また、育児をしない旦那にやってはけない行動やワンオペ育児によるリスクもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

育児をしない旦那の特徴は5つ

まず、育児をしない旦那の特徴についてご紹介します。
- 育児に参加しているつもりになっている
- 育児を自分事だと思っていない
- 育児は⼥性の仕事だと思っている
- 何をすればいいのか分からない
- 自分の都合を優先する
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.育児に参加しているつもりになっている
子育ては夫婦で協力するものですが、現実にはママの負担が大きくなりがちです。家事や育児を「手伝う」という意識のパパも多く、主体的に動く場面が少ないのが実情です。
たとえば、ゴミ出しを担当しているものの、家中のゴミを集めたり、新しいゴミ袋をセットするなどの過程をスルーしているケースも珍しくありません。
また、子どもと遊ぶのが好きなパパでも、おむつ替えや着替えの準備はママに任せ、外出先で子どもがぐずるとママに対応を任せる場合も少なくありません。
2.育児を自分事だと思っていない
ママは妊娠中から少しずつ母親としての自覚を持ち、出産後は子ども中心の生活へと自然に順応していきます。一方で、パパは育児を経験しながら徐々に親としての自覚を持つ場合が多いですが、なかにはなかなか意識が変わらず、自分の生活スタイルを優先しがちな人もいます。
その結果、ママが育児で忙しくしていても「大変そうだな」と傍観するだけで、自ら積極的に手を差し伸べないケースも珍しくありません。
3.育児は⼥性の仕事だと思っている
育児に関わろうとしない男性の多くは、家庭内の役割分担を固定観念で捉えています。自分の役割は仕事をして家族を支えることであり、家事や育児はママの仕事だと無意識のうちに思い込んでいるのです。
そのため、ママが忙しくしていても家事や育児を自分ごととして考えられません。また、幼少期の家庭環境によっても影響を受ける場合が多く、自分の父親が家のことをしていなかった場合、その姿勢を当たり前として受け継いでしまうケースもあります。
4.何をすればいいのか分からない
育児に積極的に関わらない理由の1つとして、「何をしたらいいのかわからない」というケースもあります。自分が手を出しても失敗してしまうのではないか、逆に迷惑をかけるのではないかと考え、最初から諦めてしまっているパターンです。
さらに、「勉強しよう」と思うほどの意欲もなく、結果としてママに任せっぱなしになりがちです。しかし、最初は不慣れでも、少しずつ経験を積めばできることは増えていくため、一歩踏み出す姿勢が大切です。
5.自分の都合を優先する
子どもは可愛いと思っていても、自分の時間を優先したいと考えるパパも少なくありません。育児は大変だと理解しつつも、「平日は仕事で疲れているから、休日くらいは休みたい」と自分の都合を優先してしまいがちです。
その結果、ママが休む時間もなく育児や家事に追われていても気づかない、あるいは気づいても積極的に手伝おうとしない場面が多くなります。育児は夫婦で協力して行うものですが、一方が負担を抱えすぎると不満がたまり、家庭内のバランスが崩れてしまいます。
育児をしない旦那を変えるための方法は7つ

次に、育児をしない旦那を変えるための方法についてご紹介します。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.家事の分担について話し合う
家事や育児を分担する際には、得意・不得意を考慮するようにしましょう。たとえば、料理が苦手なパパに「ごはんを作って」とお願いしても、なかなかうまくいきません。
しかし、掃除や片付けが得意な場合、そちらを任せればスムーズに役割分担ができます。また、育児に関しても最初は慣れずに戸惑うケースがあるかもしれませんが、経験を積めば自然とできることも増えていきます。
お互いに負担を減らし、無理のない範囲で協力し合うことが、家庭内のストレスを減らすポイントです。
2.一度にたくさんのことをさせない
家事に慣れていないパパにいきなり多くのことを任せても、思うようにできないかもしれません。ママが日常的にこなしている家事と同じレベルを最初から求めるのではなく、まずは1つの作業を担当してもらうのがおすすめです。
たとえば、「毎朝のゴミ出しは必ずやる」と決めてしまえば、少しずつ習慣化できます。最初は時間がかかる場合もありますが、継続によって自然と家事のスキルも向上します。無理なく続けられる範囲で協力し合い、少しずつ負担を分け合うようにしてみてください。
3.声かけを工夫する
毎日家事や育児をこなしているママからすると、パパが少し手伝っただけでは「これくらい当然」と感じてしまうかもしれません。しかし、協力しようとしているのであれば、その姿勢を前向きに受け止める寛容さも大切です。
最初は、不慣れで思うようにできない場合もあるかもしれませんが、少しずつ経験を積むと上達していきます。どんなに小さなことでも「助かったよ」「ありがとう」という声かけにより、パパも積極的に関わるようになるかもしれません。
4.子どもと夫が一緒に過ごす時間を作る
子どもと夫が一緒に過ごす時間を作るのも効果的な方法です。まずは、短時間からはじめ、子どもと二人で過ごす時間を作ることが大切です。
たとえば、お風呂に入れる、おむつを替える、寝かしつけを担当するなど、小さな育児から少しずつ慣れてもらいましょう。経験を積むことで自信がつき、自然と育児への関わりが増えていくはずです。
5.夫がやるまで放置する
パパに家事や育児を頼んだのに、なかなか動いてくれないとイライラしてしまいますよね。「あとでやる」と言われても、本当にやるのか不安になり、つい自分でやってしまう場面も少なくありません。
しかし、それでは旦那が手伝う機会を失うだけでなく、「やるつもりだったのに」とやる気をなくしてしまう可能性があります。「自分のペースでやってくれるはず」と信じ、口を出さずに待つことで、パパも責任を持って家事や育児に取り組みやすくなります。
6.育児グッズを一緒に選ぶ
育児への関心を高める方法の1つとして、育児グッズやおもちゃを一緒に選ぶのもおすすめです。どのようなアイテムが便利か話し合うことで、「一緒に子育てをしている」という実感が生まれるかもしれません。
また、パパの興味があるジャンルのおもちゃを取り入れると、自発的に遊び相手になってくれる可能性があります。さらに、パパが子どもの頃に遊んでいたおもちゃを実家から持ち帰り、一緒に楽しむのも良いアイデアです。
なお、入園準備に欠かせない名前シールについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
7.育児のルーティーンを共有する
育児の流れをスムーズにするためには、具体的なスケジュールを共有することが大切です。「お昼ごはんの後はお昼寝」「お風呂の後は歯磨き」など、時間と行動をセットで伝えると、パパも理解しやすくなります。
また、慣れるまでは子どもに話しかける形で「〇時になったからお片付けしようね」と声をかけると、自然と流れを覚えてもらえます。日々のリズムがわかるようになると、旦那も積極的に行動しやすくなり、育児への関わりが増えていくはずです。
育児をしない旦那にやってはけない行動は3つ

次に、育児をしない旦那にやってはけない行動について解説します。
- 結果的に妻がやってしまう
- 愚痴や嫌味を⾔う
- やり方が違うと怒ってしまう
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.結果的に妻がやってしまう
頼んでもなかなか動かないパパを見て、「結局私がやるしかない」と思い、先に手を出してしまうケースも少なくないですよね。しかし、そのような状況が続くと「やらなくても何とかなる」と甘えてしまい、自発的に動く機会を失ってしまいます。
「本当はやってほしいのに、つい自分で片付けてしまう」そんな悪循環を断ち切るためには、ときにはぐっとこらえて任せることも大切です。少しずつでも役割を持たせることで、パパも責任を意識するようになります。
2.愚痴や嫌味を⾔う
パパが家事や育児に協力してくれないと、不満が溜まってしまいますよね。しかし、「なんで何もしないの?」「ほかの家庭はもっと協力的なのに」と愚痴や嫌味を言ってしまうと、逆効果になる場合が多いです。
指摘された側は責められたと感じ、やる気をなくしてしまうケースも少なくありません。大切なのは、具体的にお願いすることです。「洗濯物を畳んでくれると助かる」「寝かしつけをお願いできる?」と伝えることで、旦那も動きやすくなり、自然と家事や育児に参加しやすくなります。
3.やり方が違うと怒ってしまう
パパが家事や育児を手伝ってくれた際に、完璧な仕上がりではないケースもありますよね。しかし、そのたびに「違う!」「やり直して!」と言ってしまうと、せっかくのやる気を削いでしまう結果になりかねません。
たとえやり方が違っていても、「手伝ってくれて助かったよ」「ここをこうするともっとやりやすいかも」と前向きな言葉をかけることで、旦那も次回から改善しやすくなります。
大切なのは、完璧を求めるのではなく、少しずつでも関わってもらうことです。感謝の言葉が増えると、パパも自然と協力する気持ちになっていきます。
ワンオペ育児によるリスクは3つ

最後に、ワンオペ育児によるリスクについてご紹介します。
- 育児ノイローゼになる可能性がある
- 夫への愛情が減少する
- 適切な親子関係が作れなくなる
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.育児ノイローゼになる可能性がある
育児の負担を一人で抱え込むことで、心身ともに疲れ果ててしまう場合があります。とくに「ワンオペ育児」が続くと、精神的に追い詰められ、気分が落ち込みやすくなるケースも少なくありません。
こうした状態が続くと、育児への意欲をなくしたり、体調を崩したりする可能性があります。さらに深刻な場合には、ストレスが子どもや家族との関係に悪影響を及ぼすリスクもあります。大切なのは、育児の悩みを一人で抱え込まず、家族や周囲の人と相談しながら負担を分散させることです。
なお、子育てでお悩みの方は、オンラインカウンセリングを受けるという選択肢もあります。
【エキサイトお悩み相談室】 ![]() は、いつでもどこでも実績豊富なカウンセラーに相談できる、国内最大級のオンラインカウンセリングサービスです。サービスを開始してからの約19年間で、相談件数は累計30万件を超えています。
は、いつでもどこでも実績豊富なカウンセラーに相談できる、国内最大級のオンラインカウンセリングサービスです。サービスを開始してからの約19年間で、相談件数は累計30万件を超えています。
2.夫への愛情が減少する
育児の負担を一人で抱え続けると、「なぜ私ばかりがこんなに大変なのか」「パパはなぜもっと協力してくれないのか」と不満が募ってしまうことがあります。日々の疲れやストレスが積み重なると、パパの無関心な態度や協力のなさに対してイライラが増し、夫婦の関係にも影響を及ぼします。
次第に会話が減り、気持ちのすれ違いが大きくなることで、夫婦間の関係が冷めてしまうケースも少なくありません。夫婦で協力し合い、育児の負担を分かち合うことが、関係を良好に保つポイントです。
3.適切な親子関係が作れなくなる
育児をママだけが担当していると、パパと子どもの関係が希薄になってしまう場合があります。日常的に関わる機会が少ないと、子どもは自然と世話をしてくれるママを頼るようになり、パパには距離を感じてしまいがちです。
そうなると、パパが遊びに誘っても反応が薄かったり、抱っこを嫌がったりすることが増えるかもしれません。親子の信頼関係を築くためには、日々の関わりが不可欠です。少しの時間でも子どもと触れ合い、積極的に関わることで、自然と親子の絆が深まっていきます。
まとめ

本記事では、育児をしない旦那の特徴や育児をしない旦那を変えるための方法、育児をしない旦那にやってはけない行動やワンオペ育児によるリスクをご紹介しました。
育児に積極的ではないパパの多くは、育児を自分事だと思っていない傾向にあります。また、子育てに自信がなく「何をすればいいのか分からない」と感じている人も少なくありません。さらに、「育児は夫婦で助け合うもの」という自覚がなく、自分の都合を優先してしまう人も多い傾向です。
このような場合、家事や育児の分担について一度、話し合ってみるのがおすすめです。そして、声かけの仕方を工夫してみたり、子どもとパパが一緒に過ごす時間を作ってみたりするのも効果があります。
一方で、パパに愚痴や嫌味を言ったり、やり方を指摘したりするのは逆効果です。指摘された側は責められたと感じ、やる気をなくしてしまう可能性があります。大切なのは、少しずつでも育児に関わってもらうことです。感謝の言葉が増えると、パパも自然と協力する気持ちになっていきます。
なお、子育てでお悩みの方は、オンラインカウンセリングを受けるという選択肢もあります。
【エキサイトお悩み相談室】 ![]() は、いつでもどこでも実績豊富なカウンセラーに相談できる、国内最大級のオンラインカウンセリングサービスです。サービスを開始してからの約19年間で、相談件数は累計30万件を超えています。
は、いつでもどこでも実績豊富なカウンセラーに相談できる、国内最大級のオンラインカウンセリングサービスです。サービスを開始してからの約19年間で、相談件数は累計30万件を超えています。