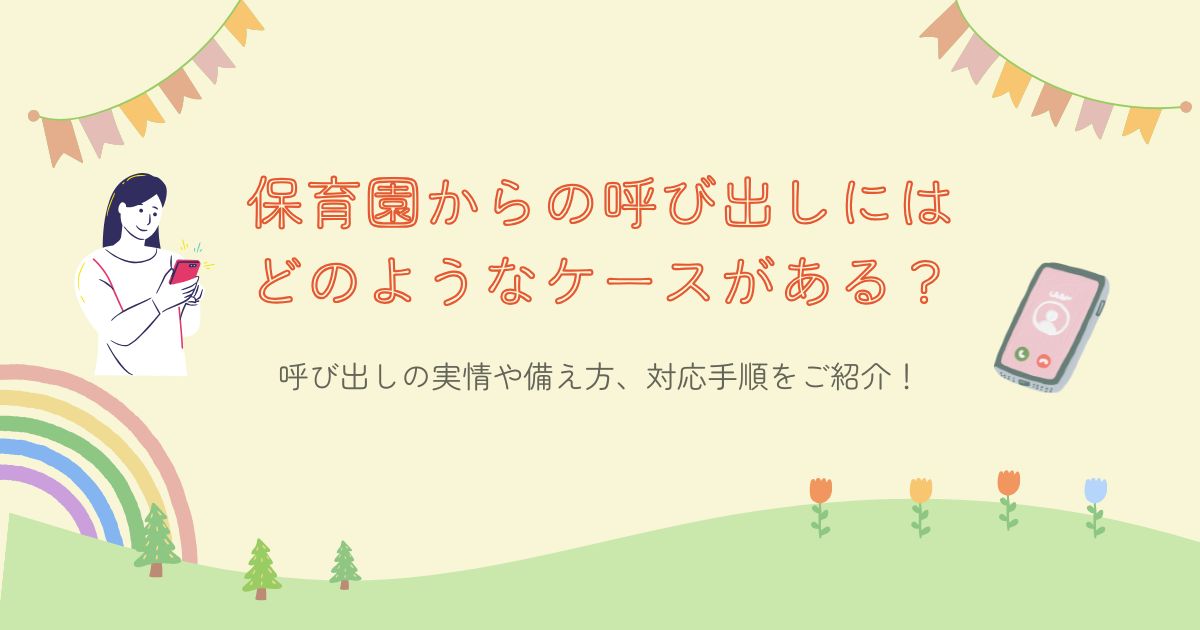保育園の入園を控えている方で、保育園の呼び出しに関して不安に感じている方もおられるのではないでしょうか。保育園からの呼び出しは、発熱や下痢などさまざまなケースがあるため、突然の呼び出しに備えておけば、スムーズな対応が可能になります。
本記事では、保育園からの呼び出しに関する実情や呼び出されるケース、呼び出しへの備え方についてご紹介します。また、呼び出しを受けた際の対応手順についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

保育園からの呼び出しに関する実情

「XTalent株式会社」が運営する共働き&子育て世代向け転職サービス「withwork」では、保育園に通う子どもを持つ親たちの仕事と育児の両立に関する実態調査を実施しています。この調査によると、入園後半年以内の親の約8割が「月に1回以上」の呼び出しを経験しており、10%以上が「月に4回以上」と回答しています。
とくに、呼び出しは冬期や入園初期に頻発している傾向です。また、夫婦間でのお迎えは「母10割」で負担の偏りが課題として浮き彫りになりました。
しかし、約7割の家庭では、子どもが2歳以上になると呼び出しの回数が減少する傾向がみられました。
参考:親のキャリアやライフにも影響を及ぼす保育園の呼び出しの実態について|XTalent株式会社
保育園からの呼び出しにはどのようなケースがある?

次は、保育園からの呼び出しが考えられるケースについて紹介します。
- 発熱
- 嘔吐・下痢
- 発疹
- ケガ
- 災害
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
発熱
多くの園では、厚生労働省や子ども家庭庁のガイドラインに従い、「37.5度以上」の発熱が確認されると保護者へ連絡し、お迎えを求めるのが一般的です。しかし、子どもによっては平熱が高い場合もあり、例外的な対応が必要となる可能性もあります。
このため、入園前の面談時に園のルールを確認して、必要に応じて相談しておくと安心です。発熱以外にも、体調不良の兆候が見られる場合には早めの対応が求められるため、保護者としても事前に方針を理解し、柔軟に対応できるよう準備しておきましょう。
嘔吐・下痢
保育園では、発熱がなくても嘔吐や下痢などの症状が見られる場合、体調不良と判断され、保護者に連絡が入るケースがあります。園に同じ症状の子どもが複数いたり、感染症の流行が疑われたりする場合は、早めの対応が求められる可能性が高いです。
一方で、単発の嘔吐や食べ過ぎによる軽い体調不良であれば、必ずしも呼び出しにつながるわけではありません。しかし、感染症の拡大を防ぐためにも、子どもの様子に変化があった際には注意が必要です。
発疹
発疹が時間とともに広がったり、かゆみや発熱を伴ったりする場合には、感染症の可能性があるため、保護者に連絡が入るケースがあります。発疹の原因はさまざまで、突発性発疹やじんましん、あせもなど軽いものから、感染症によるものまで幅広いため、医師の診断を受ける必要性があります。
また、見た目だけでは判断が難しい場合もあり、園側としても安全を優先する対応が一般的です。急な呼び出しに備え、日頃から子どもの肌の状態を確認するようにしてください。
ケガ
保育園でのけがに関しては、軽い擦り傷や打撲程度であれば、保護者への連絡のみで呼び出しには至らないのが一般的です。しかし、出血が多い場合や、腫れがひどい、強い痛みを訴えるといった症状がある場合は、病院での診察が必要と判断され、呼び出しがかかるケースがあります。
とくに、骨折や捻挫の疑いがあるケースでは、安全を考慮し、すみやかに保護者へ連絡が入る場合が多いです。園ごとに対応基準が異なるため、事前に方針を確認しておきましょう。
災害
災害が発生した際は、保育園では安全を最優先にする対応が行われ、状況によっては保護者への呼び出しがあります。地震や台風、火災などの災害時には、園ごとに決められた基準に従い、子どもを安全に保護者へ引き渡すための体制が整えられています。
大規模な災害時には、園から直接引き取りに行くのではなく、指定された避難所での受け渡しとなる場合もあるため、事前にルールを確認しておきましょう。保育園では定期的に避難訓練を実施し、安全対策を強化しています。
緊急時の対応については、保護者自身も内容を理解し、迅速に行動できるよう備えておかなければなりません。
保育園の呼び出し回数が増加しやすい時期

次は、保育園の呼び出し回数が増加しやすい時期について紹介します。
- 入園して間もない時期
- 夏(6~8月)
- 冬(12~2月)
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
入園して間もない時期
保育園に入園したばかりの時期は、子どもが体調を崩しやすく、保護者への呼び出しが頻繁に発生する場合があります。これは、新しい環境に適応する過程でストレスを感じやすかったり、集団生活の中でさまざまな病原体にはじめて触れる機会が増えたりするためです。
免疫力が十分に発達していない乳幼児は、風邪や胃腸炎などにかかりやすく、結果として欠席が続くケースも珍しくありません。しかし、多くの子どもは時間が経つにつれて免疫がつき、呼び出しの回数が徐々に減っていく傾向があります。
親としては、急な連絡に備えつつ、子どもの体調管理に気を配るようにしましょう。
なお、慣らし保育の期間については、こちらの記事で詳しく解説しています。
夏(6~8月)
夏の時期は感染症が流行しやすく、6月〜8月にかけて保育園からの呼び出しが増えると感じる保護者も多いです。手足口病やヘルパンギーナといったウイルス性の感染症が流行する季節でもあり、発熱や発疹などの症状が見られると、登園が難しくなります。
また、冬に風邪をひきやすいイメージがありますが、夏場は高温多湿の環境が影響して、体調を崩しやすい子どもも少なくありません。それぞれの体質によっても影響の受け方が異なり、特定の季節に弱い傾向がある子もいます。
冬(12~2月)
12月〜2月にかけては、気温が低く乾燥しやすいため、ウイルスが活発になりやすく、インフルエンザやマイコプラズマ肺炎などの感染症が流行しやすくなります。このため、子どもが発熱や咳などの症状を訴え、登園が難しくなるケースが多いです。
免疫力が十分に発達していない乳幼児は、一度体調を崩すと回復までに時間がかかる場合もあり、結果として休みが続く可能性もあります。冬場は感染症対策を徹底しつつ、子どもの健康管理に注意してください。
保育園からの呼び出しの備え方

次は、保育園からの呼び出しの備え方について紹介します。
- 夫婦で役割を決める
- 夫婦でスケジュールを共有する
- 職場に事情を説明する
- 親族に頼れるかを相談する
- 病児保育に登録する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
夫婦で役割を決める
保育園からの急な呼び出しに備え、事前に夫婦で対応方法について話し合うことが大切です。誰が優先的に迎えに行くのかを決めておけば、急な連絡にもスムーズに対応できます。
また、仕事のスケジュールや職場の理解度によって対応のしやすさは異なるため、お互いの状況を尊重しながら協力しましょう。最近では、父親が迎えに行くケースも増えていますが、依然として母親が担当する場合が多いのが現状です。
負担が一方に偏らないよう、家事の分担を調整したり、翌日の仕事の調整をするなど、柔軟にサポートし合う姿勢が求められます。
なお、共働きの子育てで心がけたいことについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
夫婦でスケジュールを共有する
朝の時間やスケジュールアプリなどを活用してお互いの仕事の予定を確認して、外せない会議の時間や帰宅の見込みを共有しておくと、スムーズに対応しやすくなります。共働き家庭では、どちらが迎えに行くかを柔軟に決められるよう、調整しておきましょう。
また、状況に応じて祖父母やファミリーサポートなどの協力体制を整えておくと、より安心して仕事と育児の両立ができます。
職場に事情を説明する
子どもの体調不良による突発的な早退や欠勤が避けられない場合もあるため、事前に上司や同僚へ事情を説明しておきましょう。あらかじめ周囲に理解を求めておくと、急な休みの際にも協力を得やすくなります。
また、普段から業務の進捗を共有して、いざという時に備えておくと、職場への影響を最小限に抑えられます。子どもが小さいうちは免疫力が低く、感染症にかかりやすい時期があるため、職場の理解を得るためにも、そうした背景を説明しておくことが大切です。
親族に頼れるかを相談する
保育園からの急な呼び出しには、必ずしも親が対応しなければならないわけではありません。近くに住む祖父母や信頼できる親族、ベビーシッターなどに協力をお願いすると、対応の負担を軽減できます。
しかし、保育園によっては、親以外の方が迎えに行く際には、事前の申請や身分証の提示が必要となる場合があるため、ルールを確認しておきましょう。事前に連絡手段を決めておき、スムーズに対応できるよう準備しておくと安心です。
病児保育に登録する
病児保育施設によっては、事前登録や受診が必要な場合もあるため、利用する可能性がある場合は早めに手続きや利用方法を確認しておきしょう。また、一部の病児保育室では、保育園まで迎えに行くサービスを提供しているところもあります。
仕事を継続する必要がある場合、会社の近くにドロップイン対応の病児保育があると便利です。空き状況によっては、当日の利用が可能な施設もあるため、複数の選択肢を持っておくと、急な対応にも落ち着いて対処できます。
保育園の呼び出しを受けた際の対応手順の例

保育園の呼び出しを受けた際の対応手順の例は、以下のとおりです。
- 上司への報告
保育園から連絡があった場合、すみやかに上司へ早退の旨を伝える。業務に影響が出る場合は、対応策を考え、同僚への引き継ぎを行う - 最適な移動手段の選択
子どものお迎えには、早く到着できる手段を選ぶ。タクシーが便利な場合もあるが、交通状況によっては電車のほうが確実な場合もあるため、冷静に判断することが大切 - 病院の状況を確認
移動中に、近隣の病院の空き状況を確認して、必要であれば予約を取る。感染症が疑われる場合は、適切な医療機関を選ぶ必要がある - お迎えと症状の確認
保育園に到着したら、子どもの状態を確認して、保育士から経緯を詳しく聞く。園内で流行している病気がある場合は、受診時に医師へ伝える - 医療機関の受診
必要に応じて、症状がある場合は病院を受診する。医師に保育園での流行状況を伝えると、適切な診断が受けやすくなる - 帰宅後のケアと翌日の調整
帰宅後は子どもをしっかり休ませる。また、翌日の登園可否や仕事への影響を考慮して、必要に応じて預け先を確保する
まとめ

本記事では、保育園からの呼び出しに関する実情や呼び出されるケース、呼び出しへの備え方、呼び出しを受けた際の対応手順についてご紹介しました。
「XTalent株式会社」の調査によると、入園後半年以内の親の約8割が「月に1回以上」呼び出しを経験しており、10%以上が「月に4回以上」と回答しています。看病や登園制限により「月に5日以上」も仕事に支障をきたす家庭も多く、夫婦間でのお迎えは「母10割」で負担の偏りが課題です。
また、保育園から呼び出しがあるケースとして、子どもの急な発熱や体調不良、ケガ、災害時などの際にはお迎えが必要となります。呼び出し回数が増加しやすい時期としては、入園して間もない時期や夏(6~8月)、冬(12〜2月)が多い傾向です。
呼び出しへの備えとして、夫婦間での役割を決め、当日のスケジュールを共有しておきましょう。さらに、子どもの体調不良による突発的な早退や欠勤が避けられない旨を職場へ事前に説明し、親族や病児保育、ファミリーサポートの活用も検討しておくと安心です。