保育園に通園しはじめた時期にママさんやパパさんを悩ませるのが「保育園の洗礼」です。小さな体はまだ免疫力が十分ではないため、感染リスクが高くなりがちです。なるべく元気に登園してもらうためにも、予防方法や感染時のケアについて理解を深めておきましょう。
本記事では、保育園の洗礼の主な症状やいつまで続くのかについて解説します。また、保育園の洗礼から早く回復するコツや防ぐための対策についてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
保育園の洗礼とは?

「保育園の洗礼」とは、通園をはじめた子どもが立て続けに風邪や胃腸炎などの感染症にかかる現象を指します。小さな体はまだ免疫力が十分でなく、大人なら軽く済む症状も、子どもには高熱や嘔吐といった強い症状として現れる場合があります。
さらに、園では子ども同士が密接に関わり合うため、どうしても感染リスクが高くなりがちです。体調不良が続くと不安になる保護者も少なくありませんが、焦らずにゆっくり子どもの免疫力が育つのを見守っていきましょう。
保育園の洗礼で多い症状

保育園に通う子どもは、さまざまな体調不良を経験します。たとえば、発熱や咳、鼻水は風邪の兆候としてよく見られ、とくに気道が狭い幼児は呼吸が苦しくなりやすいため注意が必要です。
また、嘔吐や下痢といった胃腸症状は感染力が強く、厚生労働省では複数回の症状があった場合、翌日の登園自粛を推奨しています。発疹が出た場合も、水疱瘡などの可能性を考慮して医療機関の受診が求められる場合があります。
保育園の洗礼はいつまで続くの?

保育園に通いはじめた子どもは、最初の数か月間、体調不良が続く場合がありますが、これは一時的なものです。繰り返し風邪や感染症にかかるうちに、少しずつ免疫がついていき、徐々に安定して登園できる日が増えていきます。
一般的には3〜6か月ほどで落ち着くケースが多いですが、体質や環境によって個人差があります。仕事や家事との両立で大変ですが、家族で協力しながらこの時期を乗り越えていきましょう。
保育園からの呼び出しが増えやすい時期

次に、保育園で呼び出しが増えやすい傾向にある時期もご紹介します。
- 夏(6~8月)
- 冬(12~2月)
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
夏(6~8月)
夏のはじめから中頃にかけては、保育園からの呼び出しが増える傾向があります。とくに、6月〜8月は気温や湿度の上昇によりウイルスが活発になりやすく、手足口病やヘルパンギーナといった夏に流行しやすい感染症が広がりやすい時期です。
このような疾患は急に発熱や発疹を伴うため、保育園でも迅速な対応が必要となり、保護者への連絡が増える一因となっています。保育園での感染症の流行状況をチェックして、手洗い・うがいなどの基本的な感染対策を徹底しましょう。
なお、呼び出しの実情や備え方については、こちらの記事でご紹介しています。
関連記事:保育園からの呼び出しにはどのようなケースがある?呼び出しの実情や備え方、対応手順をご紹介! | こそだて+
冬(12~2月)
寒さが厳しくなるこの時期は、子どもたちの免疫力も低下しやすく、インフルエンザやマイコプラズマ肺炎などの感染症が園内で広がりやすくなります。
とくに、集団生活のなかでは、咳やくしゃみを通じた飛沫感染が起こりやすいため、体調不良による早退が相次ぐことも珍しくありません。また、乾燥しやすい時期でもあるため、就寝時の乾燥にも注意してください。
保育園の洗礼から早く回復するためのコツは4つ

次に、保育園の洗礼から早く回復するためのコツをご紹介します。
- 早めに病院を受診する
- 鼻水をこまめに取り除く
- しっかり寝かせてあげる
- 水分補給をこまめにする
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
早めに病院を受診する
子どもに発熱や咳などの症状が見られた場合は、できるだけ早めに小児科を受診するようにしましょう。ただし、発熱直後ではウイルスの特定が難しい場合もあり、翌日も再診が必要になるケースがあります。
見た目に元気そうでも、体のなかでは炎症や感染が続いている場合があるため、自己判断で回復と決めつけず、医師の指示を仰ぐようにしてください。早期の対応が、重症化のリスクを減らし、安心して登園を再開する近道になります。
鼻水をこまめに取り除く
子どもの鼻水が長引くと、思わぬ体調悪化を招く場合があります。鼻水が喉に流れ込むことで咳がひどくなったり、夜間の眠りを妨げたりするほか、耳に炎症が及ぶと中耳炎、目に達すると結膜炎につながるケースも珍しくありません。
日中は元気でも、夜間にぐずったり熱を出したりする前に、こまめな鼻水のケアが大切です。家庭では、電動吸引機やポンプ式吸引機を活用し、鼻水をこまめに取り除いてあげてください。
しっかり寝かせてあげる
子どもが体調を崩した場合は、十分な休息が何より大切です。いつもより早く眠たそうにしていたら、無理に起こさずゆっくり寝かせてあげましょう。
鼻づまりがひどい場合は、上体を少し起こす姿勢で眠れるようにすると、呼吸が楽になります。ただし、枕代わりのタオルは固さや高さに注意し、窒息の危険がないように調整してください。高熱が出ると熱性けいれんのリスクもあるため、急激な体温上昇には注意が必要です。
水分補給をこまめにする
乳幼児は体の大部分を水分が占めており、大人に比べて脱水症状を起こしやすい傾向があります。発熱や嘔吐、下痢、さらには鼻水や咳などでも水分が奪われるため、体調不良のときは注意が必要です。
一度に多く飲ませるのではなく、少量ずつ頻繁に与えることで、無理なく水分補給ができます。好みの温度や飲みやすい容器を使うなど、子どもに合わせた工夫で、脱水を防ぐサポートをしてあげましょう。
保育園の洗礼を防ぐための対策は5つ

最後に、保育園の洗礼を防ぐための対策をご紹介します。
- 手洗い・うがいを習慣化する
- しっかり睡眠をとる
- 乾燥対策をする
- 予防接種を受ける
- 栄養バランスのいい食事を心がける
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
手洗い・うがいを習慣化する
感染症対策の第一歩は、毎日の手洗いとうがいの習慣づけです。保育園では、年齢に応じて手洗いのタイミングや方法を教えており、帰宅後も同じリズムで行うことで子どもの理解が深まります。
外遊びの後や食事の前には石けんを使って丁寧に洗い、うがいができる年齢になれば、帰宅後のうがいも取り入れると効果的です。家族みんなで取り組むことで、感染リスクを減らし、健康な毎日を維持することにつながります。
しっかり睡眠をとる
保育園に通いはじめた子どもにとって、安定した睡眠は体調管理の大きな鍵になります。夜更かしを避け、決まった時間に寝る習慣をつけることで、免疫力の維持にもつながります。
とくに、入園初期は生活リズムが乱れやすいため、入浴は就寝の1〜2時間前に済ませ、寝る前のテレビやスマートフォンは控えるようにしましょう。質の良い睡眠の確保により、日中も元気に園生活を送れるようになります。
なお、赤ちゃんを寝かしつけるコツについては、こちらの記事でご紹介しています。
関連記事:赤ちゃんを寝かしつけるコツは5つ|寝かしつけるアイデアや注意したい行動もご紹介します!
乾燥対策をする
冬の乾燥した空気はウイルスの活動を助けてしまうため、室内の湿度管理がとても重要です。とくに、風邪やインフルエンザの流行が心配な時期は、加湿器を活用したり、室内干しで自然に湿度を上げたりする工夫が役立ちます。
湿度は50〜60%を保つのが理想とされており、水分補給も忘れずに行うことで喉の乾燥を防げます。できることから取り入れて、健康に冬を乗り切る環境づくりを心がけましょう。
予防接種を受ける
予防接種は、子どもを感染症から守る重要な手段の1つです。決められた時期に接種することで、病気そのものの発症を防ぐだけでなく、万が一かかってしまった場合でも重症化を防ぐ効果が期待されます。
保育園では集団生活を送るため、さまざまなウイルスに触れる機会が多くなります。周囲への感染拡大を防ぐためにも、接種可能な予防接種は早めに済ませておくようにしましょう。
栄養バランスのいい食事を心がける
子どもの免疫力を保つためには、日々の食事がとても重要です。とくに、腸内環境を整えることで、体調を崩しにくくする効果が期待できます。
発酵食品や食物繊維を含む食材を取り入れることで、善玉菌が増え、腸内のバランスが整いやすくなります。忙しい朝でも、バナナやおにぎりなど手軽なもので構わないので、何かしら口にする習慣をつけましょう。無理のない範囲でバランスのよい食事を意識することが大切です。
まとめ

本記事では、保育園の洗礼の主な症状や続きやすい期間、保育園の洗礼から早く回復するコツや防ぐための対策についてご紹介しました。
「保育園の洗礼」は、通園をはじめた子どもが立て続けに風邪や胃腸炎などの感染症にかかる現象を指します。小さな体はまだ免疫力が十分ではないため、これらの感染リスクが高くなりがちです。
しかし、これは一時的なもので、繰り返し風邪や感染症にかかるうちに、少しずつ免疫がついていき、徐々に安定して登園できる日が増えていきます。一般的には3〜6か月ほどで落ち着くケースが多いとされていますが、体質や環境によって個人差がある点を理解しておきましょう。
また、感染を防ぐためには、手洗い・うがいを習慣化し、予防接種もできるだけ早めに済ませるようにしてください。生活リズムにも注意し、十分な睡眠時間を確保することが大切です。さらに、栄養バランスのいい食事を心がけ、腸内環境を整えてあげることが重要なポイントです。
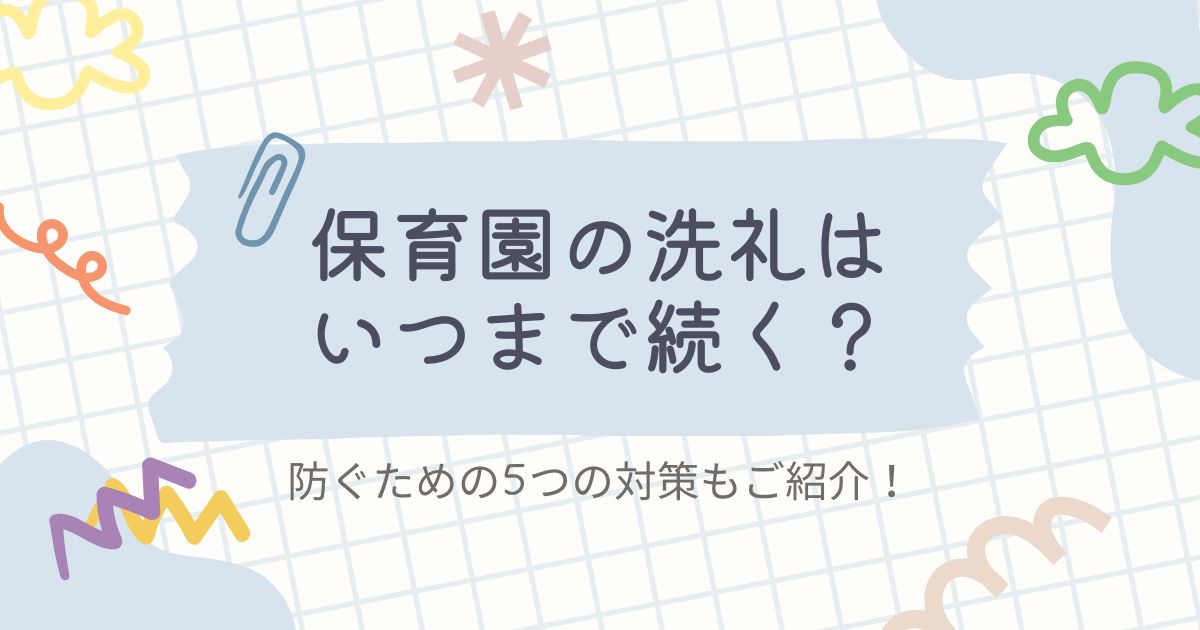
-1-120x68.jpg)
