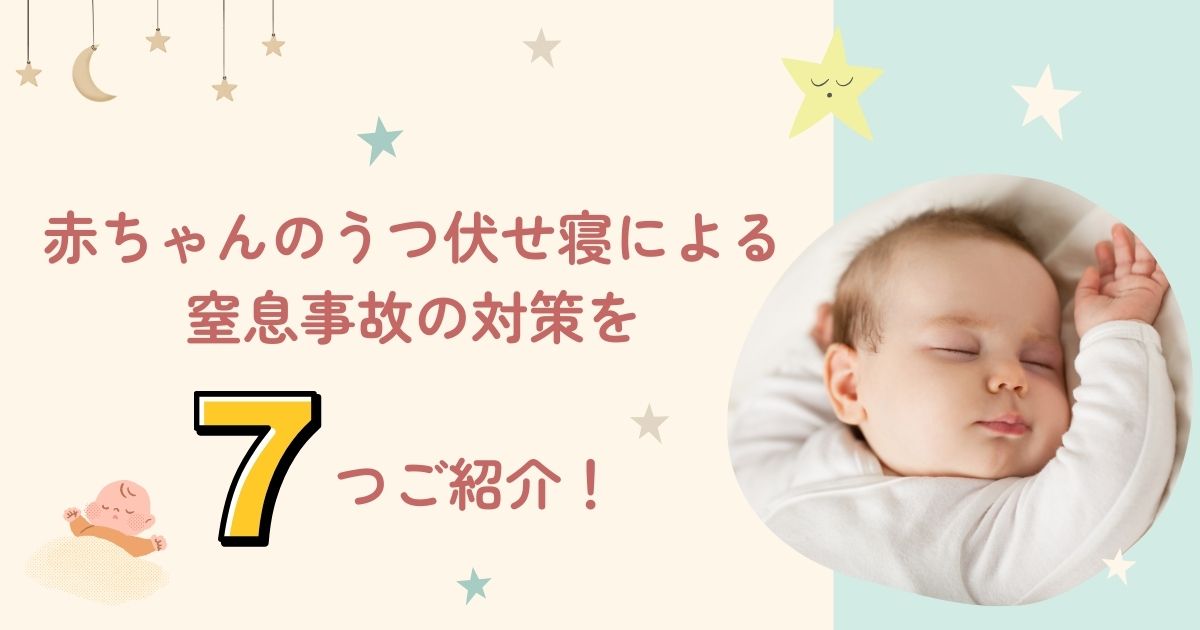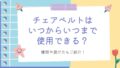うつ伏せ寝は、赤ちゃんが寝返りを打つという筋力の成長を示す自然な動作の1つですが、うつ伏せ寝には、窒息や乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクが存在します。このため、赤ちゃんの命を守るためにも、うつ伏せ寝を防ぐための対策を理解しておいてください。
本記事では、赤ちゃんがうつ伏せ寝になる原因やリスク、注意が必要な時期をご紹介します。また、赤ちゃんのうつ伏せ寝による窒息事故の対策も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
赤ちゃんがうつ伏せ寝になる原因とは?

赤ちゃんがうつ伏せ寝になる原因のひとつは、寝返りによる姿勢の変化です。成長に伴って自分で体を動かせるようになると、心地よさを求めてうつ伏せになる場合があります。
しかし、まだ体の動きが未熟なうちは仰向けに戻れず、その姿勢のまま長時間過ごしてしまうケースが多く見られます。うつ伏せの姿勢で安心感を覚える赤ちゃんもいますが、安全面を考えると注意が必要です。
このため、過ごしやすい温度や寝具の硬さを調整して、快適な仰向け寝の環境を整えてあげることが大切です。
赤ちゃんが寝返りをし始める時期

赤ちゃんが寝返りをし始める時期は、体の発達に伴い日々の動きが活発になります。生後2か月以降、手足の動きが勢いを増して、横向きになる様子が見られると寝返りの兆しとなります。
こうした動きは筋力の成長を示す自然な動作の1つですが、睡眠中にうつ伏せ姿勢になる場合もあるため注意が必要です。安全のためには、寝ている間の様子をこまめに確認して、必要に応じて仰向けに戻してあげるようにしましょう。
さらに、起きている間も、ふとしたきっかけで姿勢が変わる場合があるため、常に見守る姿勢を忘れないようにしてください。
赤ちゃんのうつ伏せ寝によるリスク

次は、赤ちゃんのうつ伏せ寝によるリスクについて解説します。
- 窒息する危険性がある
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクが高まる
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
窒息する危険性がある
赤ちゃんがうつ伏せで寝ている状態は、呼吸が妨げられる危険があるため十分な注意が必要です。寝返りが未発達な時期は、顔が布団などに埋まりやすく、窒息のリスクが高まります。
このような状況を防ぐには、敷布団は固めのものを使用して、シーツやカバー類にたるみがないか確認しましょう。また、赤ちゃんの衣類もゆとりがありすぎると顔まわりにかかるおそれがあるため、体に合ったサイズ選びが大切です。
自分で寝返りができるようになるまでは、就寝中の姿勢を見守る習慣を持ち、安全な環境を整えてあげると安心につながります。
乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクが高まる
厚生労働省のデータによると、令和5年に乳幼児突然死症候群で亡くなった乳幼児は、48人と決して低い数字ではありません。乳幼児突然死症候群(SIDS)は、生後数か月の赤ちゃんに発症するリスクが高いため、入念な対策が欠かせません。
そのなかでも、うつ伏せ寝は、SIDSの発症リスクを高める要因として多くの研究で指摘されています。睡眠中に呼吸が妨げられる姿勢は避けるべきであり、赤ちゃんはできるだけ仰向けで寝かせるよう心がけましょう。
また、周囲の喫煙環境も影響を与えるとされているため、妊婦や乳児の近くでの喫煙は控えるのが望ましいです。
参考:令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況|厚生労働省
うつ伏せ寝に注意が必要な時期はいつまで?

赤ちゃんの安全な睡眠姿勢として、厚生労働省やこども家庭庁では「あおむけ寝」を強く推奨しています。これは、乳幼児突然死症候群(SIDS)や窒息のリスクを減らすための大切な予防策です。
こども家庭庁では寝返りができる・できないに関わらず、「原則1歳まではあおむけ寝」を推奨しています。また発達状況に応じて1歳以上でも同様の対策をするように呼びかけています。
赤ちゃんのうつ伏せ寝による窒息事故の対策は7つ

最後に、赤ちゃんのうつ伏せ寝による窒息事故の対策について紹介します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
腹這いの練習をする
赤ちゃんの成長に合わせて、起きている時間を活用した腹ばいの練習を取り入れると、うつ伏せ寝によるリスク軽減につながります。生後1か月ごろから、機嫌の良いタイミングに短時間からはじめるのがポイントです。
顔を横に向けた状態でうつ伏せにして、無理のない範囲で徐々に時間を延ばしていきましょう。この練習により、首や肩まわりの筋肉が発達して、自力で頭を持ち上げる力がついてきます。習慣化すると、将来的な寝返りや安全なうつ伏せ姿勢にもつながりやすくなります。
顔の周辺に物を置かない
赤ちゃんの安全な睡眠環境を整えるためには、ベッドにやわらかい物を置かないようにしましょう。ぬいぐるみやクッション、タオルなどが赤ちゃんの顔まわりにあると、寝返りを打った際に口や鼻を塞いでしまうおそれがあります。
窒息のリスクを避けるためにも、赤ちゃんの寝床はできるだけすっきりと保ちましょう。お気に入りのアイテムが必要な場合は、眠った後にそっと取り除く工夫が必要です。枕も基本的には不要で、使う際には平らで厚みが出ないよう配慮してください。
挟まりやすいような隙間を作らない
ベビーベッドの隅や壁との間に空間があると、赤ちゃんが頭や体を挟んでしまう危険があります。こうした隙間は、しっかりと硬めの素材でふさぎ、やわらかいクッションなどは避けるようにしましょう。
やわらかいものは窒息のリスクを高めてしまうため、専用の隙間対策グッズを活用するのが理想的です。また、赤ちゃんが寝返りで転落しないよう、柵やガードを設置しておくようにしましょう。
敷布団やマットレスは硬いもの選択する
赤ちゃんが寝るマットレスや敷布団がやわらかすぎると、うつ伏せになった際に顔が沈み込み、呼吸が妨げられる危険があります。このため、体が深く沈み込まない硬めの素材を選ぶようにしてください。
また、枕は不要で、掛け布団は赤ちゃんが簡単に動かせるような軽量のものを使用しましょう。寝具のサイズがベビーベッドに合っているかも確認し、隙間ができないように注意を払うようにしてください。
背中が暑くならないようにする
赤ちゃんがうつ伏せ寝になりやすい背景には、背中に熱がこもることが関係している場合があります。赤ちゃんは体温調節が未熟なため、室温が高すぎたり厚着をしていると、無意識のうちに快適な姿勢を探して寝返りを打ちやすくなります。
こうした状況を防ぐには、季節ごとの適切な室温設定が欠かせません。冬は20〜25度、夏は25〜28度を目安にして、赤ちゃんが汗をかいていないか、手足が冷えていないかをこまめにチェックしましょう。また、服装も通気性のよい素材を選び、快適な睡眠環境を整えてあげることが大切です。
ベビーベッドに寝かせる
赤ちゃんと一緒に寝ていると、保護者が知らぬ間に寝入ってしまう場合も珍しくありませんが、その際に赤ちゃんを覆ってしまう危険があります。安全を確保するには、赤ちゃんを大人とは別のベビーベッドで寝かせるのがおすすめです。
ベビーベッドを選ぶ際は、「PSCマーク」が表示されている製品を選ぶと安心です。このマークは、製品が国の安全基準を満たしていることを示す証です。また、使用時は柵をしっかりと立て、赤ちゃんが隙間に入り込まないように、寝具の配置にも気を配りましょう。
寝返り予防になる工夫をする
赤ちゃんのうつ伏せ寝を避けるためには、寝返りを防ぐちょっとした工夫が役立ちます。たとえば、体の左右に支えを置くと、仰向けの姿勢を保ちやすくなります。
しかし、安全性を確保するためには、顔の周囲には物を置かず、支えは肩より下の位置に設置しましょう。赤ちゃんが自力で動けるようになるまでは、こうしたサポートが必要です。さらに、夜間も赤ちゃんの様子を定期的に確認するようにしましょう。
まとめ

本記事では、赤ちゃんがうつ伏せ寝になる原因やリスク、注意が必要な時期、窒息事故の対策についてご紹介しました。
赤ちゃんのうつ伏せ寝は、生後2か月以降の寝返りを覚え始めた時期に多く見られます。寝返りは、筋力の成長を示す自然な動作の1つですが、うつ伏せ寝による窒息事故もあるため、細心の注意が必要です。
首や呼吸機能が未発達な時期にうつ伏せの姿勢で眠ってしまうと、窒息やSIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクが高まります。このため、こども家庭庁では、1歳までは「あおむけ寝」を推奨しています。
また、窒息事故を防ぐためには、腹這いの練習や顔周りの安全確保、硬めの寝具選びなどの対策が不可欠です。さらに、暑くなりすぎないような環境づくりや、ベビーベッドの活用も効果的です。赤ちゃんの命を守るために、今できる工夫を見直してみましょう。