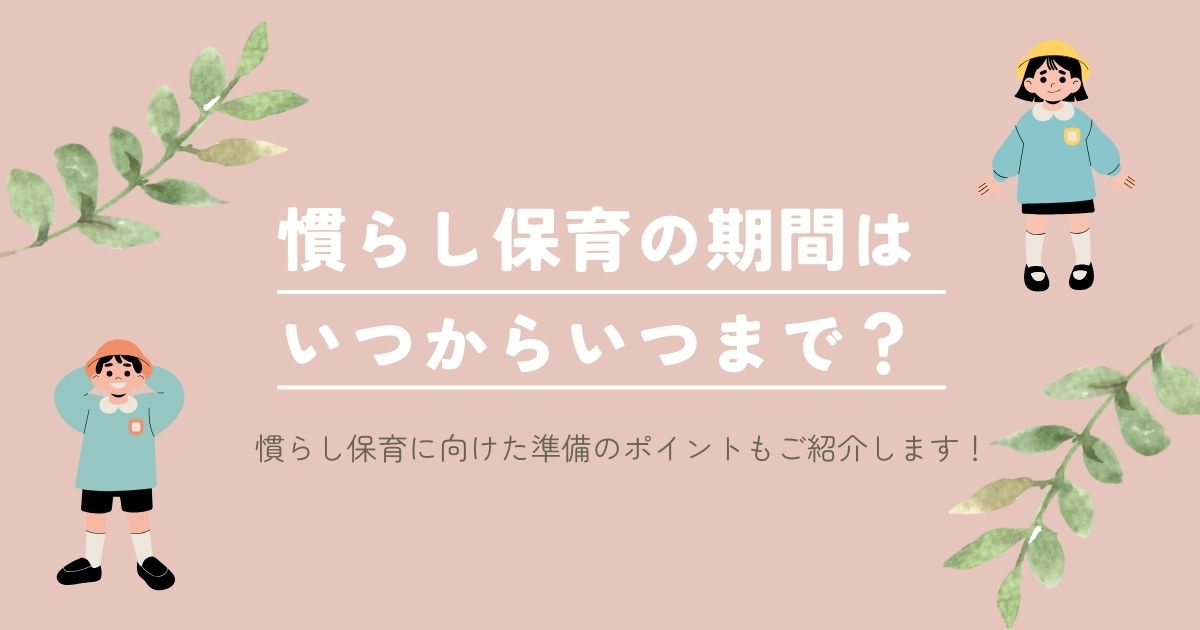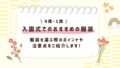慣らし保育は、はじめて親と離れる時間を過ごす子どもにとって、スムーズに新しい環境に馴染むための大切なステップです。具体的にどのくらいの期間が必要なのか、どのような準備をすればよいのか気になりますよね。
本記事では、慣らし保育の期間や慣らし保育に向けた準備のポイントをご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

慣らし保育とは?

保育園に入園した際には、子どもが新しい環境に慣れるまでの期間が必要です。このため、「慣らし保育」として、最初の1〜2週間は通常の保育時間を短縮して、段階的に延ばす対応をしているケースが多いです。
初日は、短時間の滞在からはじめ、徐々に園で過ごす時間を増やしていき、子どもが無理なく新しい生活に適応できるよう配慮されています。保護者にとっても、少しずつ子どもを預ける時間を伸ばしていけば、安心して園に送り出しやすくなります。
慣らし保育がない場合もある
慣らし保育の実施状況は自治体や保育園によって異なり、一部では慣らし保育の期間を設けていない場合もあります。このため、入園前に保育園の方針を確認しておきましょう。
慣らし保育がない園の場合、一時保育を利用して事前に園の環境に慣れさせるのも1つの方法です。また、自治体によっては復職日からしか保育を開始できないケースもあるため、職場と相談して、復職日と入園スケジュールが無理なく調整できるように計画を立てておきましょう。
慣らし保育の目的や必要な理由

次は、慣らし保育の目的や必要な理由について解説します。
- 子ども
- 保護者
- 保育士
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
子ども
慣らし保育では、家庭とは異なる保育園の雰囲気に慣れ、保護者と離れて過ごすことへの不安を少しずつ軽減していきます。保育士との信頼関係を築きながら、集団生活のルールや園での生活リズムに馴染んでいくのが目的です。
また、子どもによって適応のスピードは異なり、すぐに慣れる子もいれば時間がかかる子もいます。それぞれのペースを尊重しながら、温かく見守ることが大切です。
保護者
慣らし保育は、子どもと離れるのに慣れるだけでなく、送り迎えの流れを把握して、生活リズムの変化に適応していく必要があります。朝は準備に追われるため、スムーズに動けるような工夫が欠かせません。
また、保育士との信頼関係を築き、園での様子や子どもの変化について情報の共有も大切です。慣らし保育の期間を活用しながら、少しずつ新しい生活のペースをつかんでいきましょう。
保育士
新年度には多くの新入園児が加わり、保育士はそれぞれ子どもの性格や生活リズムを把握しながら関係を築いていきます。慣らし保育があれば、保育士も子どもとの関わり方を丁寧に考えられ、保護者ともじっくりコミュニケーションをとれます。
また、新年度はクラス替えや進級による変化もあり、在園児にとっても新しい環境に順応する期間が必要です。新入園児の保育時間が短縮されると、保育士も落ち着いて対応できるため、よりスムーズに新年度の保育が進んでいきます。
慣らし保育の期間はいつからいつまで?

次は、慣らし保育の期間について解説します。
- スケジュール例
- 育休中の慣らし保育も可能
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
スケジュール例
慣らし保育の期間やスケジュールは園によって異なりますが、一般的には1〜2週間程度をかけて徐々に保育時間を延ばしていく場合が多いです。たとえば、初日は1〜2時間の短時間保育から始まり、数日かけて昼食の時間まで延長されます。
その後、昼食後も園で過ごす時間を増やし、最終的にはお昼寝を含めた長時間保育へと移行していきます。子どもの適応状況に応じてスケジュールが調整される場合もあるため、保育士と相談しながら進めましょう。
育休中の慣らし保育も可能
育児休業中であれば、子どもの体調不良やスケジュール変更にも柔軟に対応しやすく、無理のないペースで進められるのがメリットです。厚生労働省の規定では、慣らし保育のために育休中の入園が認められるケースもあり、事前に確認しておくと安心です。
また、子どもが環境に慣れるまでの時間の確保により、保護者も仕事復帰後の負担を軽減しやすくなります。無理のないスケジュールで準備を進めましょう。
慣らし保育に向けた準備のポイントは3つ

次は、慣らし保育に向けた準備のポイントについて解説します。
- 生活リズムを整える
- 通園が楽しみになるような声かけをする
- 持ち物に名前を記入する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
生活リズムを整える
0〜2歳の子どもは、食事や着替えに時間がかかる場合が多いため、朝の支度に余裕を持たせる工夫が必要です。起床時間や朝食のタイミングを一定にして、登園時間を想定したスケジュールで過ごすと、子どもも徐々に新しいリズムに慣れていきます。
保護者も家事や自身の準備を考慮しながら、無理のない流れを作ることが大切です。事前にシミュレーションをしながら、少しずつ新しい生活の準備を整えていきましょう。
通園が楽しみになるような声かけをする
慣らし保育が始まる前に、子どもに保育園の楽しさを伝えておくと、スムーズに新しい環境に馴染みやすくなります。「どんな遊びができるかな?」「先生とお友だちに会えるね!」など、ポジティブな話題を通じて、保育園がワクワクする場所だと感じられるようにしましょう。
はじめての場所に不安を感じやすい子どももいるため、焦らず少しずつ気持ちの準備を進めることが大切です。保護者も一緒に楽しみにする姿勢を見せると、子どもも前向きな気持ちで慣らし保育を迎えられます。
持ち物に名前を記入する
保育園に持っていくすべての持ち物には、はっきりと名前を書いておきましょう。園では多くの子どもたちが同じような持ち物を使うため、間違いを防ぐためにも名前を見えやすい場所に記入しなければなりません。
オムツや衣類、タオルなど、日常的に使うものはすぐに確認できるようにしておけば、保育士もスムーズに対応できます。園によって記名のルールが異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
なお、名前シールのおすすめについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
慣らし保育でよくある困りごとと対処法

次は、慣らし保育でよくある困りごとと対処法について解説します。
- 子どもがぐずったり泣き続ける
- 環境の変化に対応できない
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
子どもがぐずったり泣き続ける
入園当初、保護者と離れるのが不安で泣いてしまう子どもは少なくありません。泣かれると保護者もつらく感じますが、子どもが新しい環境に適応するための大切なステップと捉えて、安心できる言葉をかけてあげましょう。
保護者が不安そうにしていると、その気持ちが子どもにも伝わり、余計に不安を感じてしまいます。笑顔で「いってらっしゃい!」と送り出し、子どもが少しずつ慣れていくのを温かく見守る姿勢が大切です。
環境の変化に対応できない
慣らし保育と仕事復帰が重なると、生活が一気に変わり、心身ともに負担を感じる場合があります。朝の準備や送り迎え、仕事との両立など、慣れるまで大変に思う場合は、焦らずに「少しずつ順応していけば大丈夫」と気持ちを落ち着かせましょう。
最初は戸惑うことがあっても、時間が経つにつれて自然と新しい生活リズムに馴染んでいくものです。無理をせず、自分のペースで新しい環境に適応していくことが大切です。
慣らし保育の終了を見極めるポイントは3つ

最後に、慣らし保育の終了を見極めるポイントについて紹介します。
- 1日中泣かずに過ごせる
- 飲食ができる
- お昼寝ができる
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1日中泣かずに過ごせる
保育園の環境に慣れてくると、少しずつ泣く時間が減り、落ち着いて過ごせるようになります。登園時に泣いてしまっても、保護者が見えなくなると気持ちを切り替え、遊びはじめる子も多いです。
最初のうちは不安で泣き続ける場合もありますが、抱っこをしたり優しく声をかけたりすると、少しずつ安心できる時間が増えていきます。泣き止むまでの時間が短くなってきたら、園の生活に適応しはじめたサインです。
このため、お迎え時に保育士から日々の様子を伝えてもらい、状況を把握しておきましょう。
飲食ができる
慣らし保育が始まると、環境の変化による緊張から、おやつや給食を食べたがらない子もいます。はじめての集団生活では、食事の時間に戸惑ったり、慣れない雰囲気に落ち着かなかったりする場合もあります。
しかし、少しずつ園の雰囲気に慣れてくると、食事の量が増えていくケースが多いです。最初は飲み物だけ摂れるようになり、次第に好きなものから食べはじめるようになります。
完食できる日が増えたり、おかわりをする姿が見られるようになったら、大きな成長のサインです。お迎えの際に「今日はしっかり食べましたよ」と報告があれば、たくさん褒めてあげましょう。
お昼寝ができる
睡眠は、安心できる場所でないと、大人でもなかなか眠れないように、子どもも緊張が解けなければ寝つきにくいものです。慣らし保育の期間中、次第に落ち着いてお昼寝できるようになったり、布団に横になって静かに過ごせたりするようになれば、保育園が安心できる場所になってきた証拠です。
もし、寝つきが悪い場合は、家庭での入眠習慣を保育士と共有しながら、園でもリラックスできる環境を整えていきましょう。
まとめ

本記事では、慣らし保育の期間や慣らし保育に向けた準備のポイントをご紹介しました。
慣らし保育では、最初の1〜2週間は通常の保育時間を短縮して、段階的に延ばす対応をしている園が多いです。初日は、短時間の滞在からはじめ、徐々に園で過ごす時間を増やしていき、子どもが無理なく新しい生活に適応できるよう配慮されています。
また、慣らし保育に向けた準備としては、生活リズムを整え、通園が楽しみになるような声かけが欠かせません。さらに、持ち物に名前を記入するなど、スムーズな登園のための準備も進めましょう。
なお、「お名前シール製作所byレスタス」では、他店にはない可愛いデザインのお名前シールを787種類という豊富なラインナップで提供しています。最短で翌日出荷にも対応しており、インターネット国内販売シェアNo.1という圧倒的人気を誇ります。