子どもの指先がかたくなったり赤くなったりしているのを見て、心配されている方も多いのではないでしょうか。これは、指しゃぶりが原因でできる「吸いだこ」の可能性があり、長引くと皮膚のトラブルに発展するリスクがあります。
本記事では、子どもの指に吸いだこができる理由や指しゃぶりをする主な理由、やめさせたい年齢をご紹介します。また、指しゃぶりをやめさせる方法やNGな対応も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

子どもの指に吸いだこができる理由とは?

子どもが無意識に指をしゃぶり続けると、皮膚が厚くなったり赤みを帯びたりする場合があります。このような変化は、繰り返しの摩擦や吸引による影響で生じるもので、ひび割れを伴う可能性があります。
見た目には気付きにくく、子ども自身が不快感を訴えないため、発見が遅れがちです。多くの場合は成長とともに自然に収まりますが、症状が長引くようであれば、生活習慣や周囲の環境に目を向け、改善のきっかけを探りましょう。
指しゃぶりをやめさせたい年齢

指しゃぶりは幼少期によく見られる行動ですが、長く続くと歯並びやかみ合わせに悪影響をおよぼす可能性があります。3歳を過ぎても習慣的に行っている場合、口腔への影響が大きくなるため、少しずつやめるための工夫や支援が必要です。
また、吸う力が強く「吸いだこ」ができているようなケースでは、専門家への相談も視野に入れましょう。日本小児歯科学会も、4歳以降の継続には積極的な対応を呼びかけています。
指しゃぶりをする主な理由は5つ

次は、指しゃぶりをする主な理由について解説します。
- 安心感を求めている
- 習慣になっている
- 退屈している
- 歯にかゆみがある
- 眠くなっている
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
安心感を求めている
指しゃぶりは、幼い子どもが心を落ち着けるために自然と行う行動の1つです。眠気を感じたときや不安を抱えたときに、自分の指を口に入れることで安心感を得ようとします。
これは、乳児期に母乳を通じて得ていた心地よさを再現しようとする本能的な動きともいえます。成長の過程で徐々に頻度は減っていきますが、子どもの心のサインとして見守る姿勢も大切です。
習慣になっている
赤ちゃんの頃から続く指しゃぶりは、安心感を得るための習慣として深く根づいている場合があります。無意識のうちに「指を吸うと気持ちが落ち着く」と脳が覚えており、それが癖となって続いてしまうケースも少なくありません。
成長とともに自然にやめられる子もいますが、癖として定着している場合には、焦らず段階的にサポートしましょう。
退屈している
子どもが指しゃぶりをする背景には、遊びに飽きてしまったときや、大人が手を離せない時間帯に気を紛らわせる手段として指をくわえる場合があります。このような時は、生活リズムの見直しや外遊びの時間を増やすなどの工夫が必要です。
また、指しゃぶりの兆候が見られた場合、軽く手を握ってあげれば、気持ちを切り替える助けになります。
歯にかゆみがある
乳歯が生えはじめる時期には、歯茎にむずがゆさを感じる子どもが多く、その不快感を和らげるために指しゃぶりをする場合があります。これは、成長にともなう自然な反応であり、指を口に入れたり歯茎を押したりする行動が見られても、それほど心配はいりません。
多くの場合、歯の生えそろいとともにそうした行動も落ち着いていくため、様子を見ながら見守りましょう。
眠くなっている
2歳頃の子どもが指しゃぶりをするのは、眠気を感じて心を落ち着けようとしているサインであるケースが多いです。昼寝や就寝前に見られる場合は、安心を求める気持ちの表れともいえます。
このような場合は、無理にやめさせようとせず、そっと寄り添いながら絵本を読んだり、ぬくもりを感じられるようにそばにいてあげると、穏やかな眠りにつきやすいです。こうした対応が、安心感につながり、指しゃぶりの頻度を減らす助けにもなります。
なお、指しゃぶりする子の特徴や理由については、こちらの記事でもご紹介しています。
指に吸いだこができた場合の見分け方と対処法

指しゃぶりを頻繁に行うと、特定の指に「吸いだこ」ができる場合があります。これは、皮膚が繰り返し刺激を受けるため赤くなったり、硬くなったりする状態です。
多くの場合は自然に改善しますが、ひび割れや出血が見られる場合は、保湿剤を使って皮膚を守るようにして、患部を清潔に保ちつつ様子を見ましょう。症状が悪化したり長引いたりするようであれば、小児科や皮膚科の受診を検討すると安心です。
指しゃぶりをやめさせる5つの方法

次は、指しゃぶりをやめさせる方法について紹介します。
- 手や指を使った遊びをする
- スキンシップを多くとる
- 寝ているときに手を握ってあげる
- 寝る前に絵本を読んであげる
- 指しゃぶり防止グッズを使用する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
手や指を使った遊びをする
日中に指しゃぶりの習慣が見られる場合は、手や口を使う遊びを通して自然に意識をそらす工夫が役立ちます。たとえば、ブロックや折り紙、パズルといった指先を使う遊びは集中力も養え、指しゃぶりの回数を減らす助けになります。
また、しりとりやリズム遊びなど、口を動かす活動も効果的です。子どもが楽しく取り組める環境を整えると、無理なく習慣の見直しにつなげられます。
スキンシップを多くとる
指しゃぶりが習慣化している様子が見られたら、手を優しく握ったり、そっと撫でてあげたりするなどのスキンシップを意識してみましょう。不安や緊張を感じている子どもにとって、親のぬくもりは大きな安心材料です。
また、指先を使う遊びに誘導すると、気持ちをほかの行動に向けられます。心が安定してくると、自然と指しゃぶりの回数も減る場合があるため、焦らず寄り添う姿勢が大切です。
寝ているときに手を握ってあげる
夜間に指しゃぶりをする子どもには、眠る前にそっと手を握ってあげると安心感を与えやすくなります。親のぬくもりを感じれば、心が落ち着き、指しゃぶりをせずに眠りにつける場合もあります。
寝かしつけの際は、親がリラックスした気持ちで接することが大切です。不安や緊張が伝わると、かえって子どもの落ち着きが失われてしまう場合もあるため、穏やかな時間を共有するようにしましょう。
寝る前に絵本を読んであげる
眠る前に指しゃぶりが見られる子どもには、絵本の読み聞かせを取り入れてみるのがおすすめです。物語に集中すると、自然と指しゃぶりの習慣を忘れやすくなります。
また、親子でゆっくりと過ごす時間は、子どもに安心感を与え、心を落ち着かせる効果も期待できます。さらに、寝かしつけの際は、親がリラックスした雰囲気で接しましょう。穏やかなやりとりが、子どもの不安を和らげ、快適な眠りにつながります。
指しゃぶり防止グッズを使用する
指しゃぶりがなかなかやめられない場合には、防止グッズを活用する方法もあります。専用のマニキュアやクリーム、手袋、指キャップなど、さまざまなタイプがあり、素材には口に入れても安心な成分が使われている場合が一般的です。
しかし、こうしたグッズはほかの対応を試しても効果が見られなかったときの選択肢として検討するのが望ましいです。また、使用する際は対象年齢や成分表示をよく確認して、説明書を読んで正しく使いましょう。
色々試しても上手くいかなくて、本当に悩みますよね😥でも、もう一人で抱え込まないでください。多くのママさんが最終的にたどり着くのが、子どもに合った防止グッズなんです👍安全な成分で作られたやさしいグッズで、親子でストレスなく指しゃぶり卒業を目指しませんか✨
指しゃぶりをやめさせるときにNGな対応方法

最後に、指しゃぶりをやめさせるときにNGな対応方法について紹介します。
- 怒る・叱るなどの否定的な声掛けをする
- 無理やり指を引き抜く
- 年齢を引き合いに出して恥ずかしさをあおる
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
怒る・叱るなどの否定的な声掛けをする
指しゃぶりをやめさせたい一心で「やめなさい」や「きたないよ」といった否定的な声かけをしてしまうと、子どもの心に不安を与え、指しゃぶりの頻度が増える場合があります。子どもは叱られると自尊心が傷つき、別の癖に移行してしまう可能性もあるため注意が必要です。
子どもが安心できるような声かけや、気持ちを受け止める姿勢を大切にして、無理のないペースで見守ることが指しゃぶりの改善には効果的です。
無理やり指を引き抜く
指しゃぶりをしている子どもの指を無理に引き抜くのは、逆効果になる場合があります。眠る前のタイミングでは、指しゃぶりが安心感を与える手段になっている場合が多く、無理にやめさせようとすると不安が強まり、寝つきが悪くなる場合もあります。
また、無理に引き抜く行為が遊びのように感じられてしまい、かえってやめにくくなるケースも少なくありません。子どもの気持ちに寄り添い、自然にやめられるよう穏やかに対応しましょう。
年齢を引き合いに出して恥ずかしさをあおる
「もう〇歳なのにまだ指しゃぶりしてるの?」といった年齢を意識させる声かけは、子どもの自己肯定感を傷つけてしまいかねません。否定ではなく、小さな変化や努力に目を向けて「今日は少し我慢できたね」と、前向きな言葉をかけてあげましょう。
このような積み重ねが、子ども自身の意欲を引き出して、自然と指しゃぶりを減らすきっかけになります。成長の過程を温かく見守る姿勢を心がけましょう。
まとめ

吸いだこは、子どもが指しゃぶりを続けることで皮膚が厚くなったり赤みを帯びたりしてできます。3歳を過ぎても習慣的に行っている場合、皮膚トラブルや口腔への影響が大きくなるため、少しずつやめるための工夫や支援が必要です。
指しゃぶりをやめさせるには、スキンシップを増やしたり、寝る前の習慣を見直したりすると、自然な卒業をサポートできる可能性があります。しかし、指しゃぶりがやめられない場合には、防止グッズを活用するのも1つの手段です。
専用のマニキュアやクリーム、手袋、指キャップなど、さまざまなタイプがあるため、使用する際は対象年齢や成分表示をよく確認して、正しく使用しましょう。
ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます😊子どもの指しゃぶり、そして吸いだこの悩み、解決のヒントは見つかりましたか?無理に叱るのではなく、お子さまの気持ちに寄り添いながら、便利なグッズの力を借りるのも賢い選択です。親子の笑顔のために、今日からできること、始めてみませんか?👣
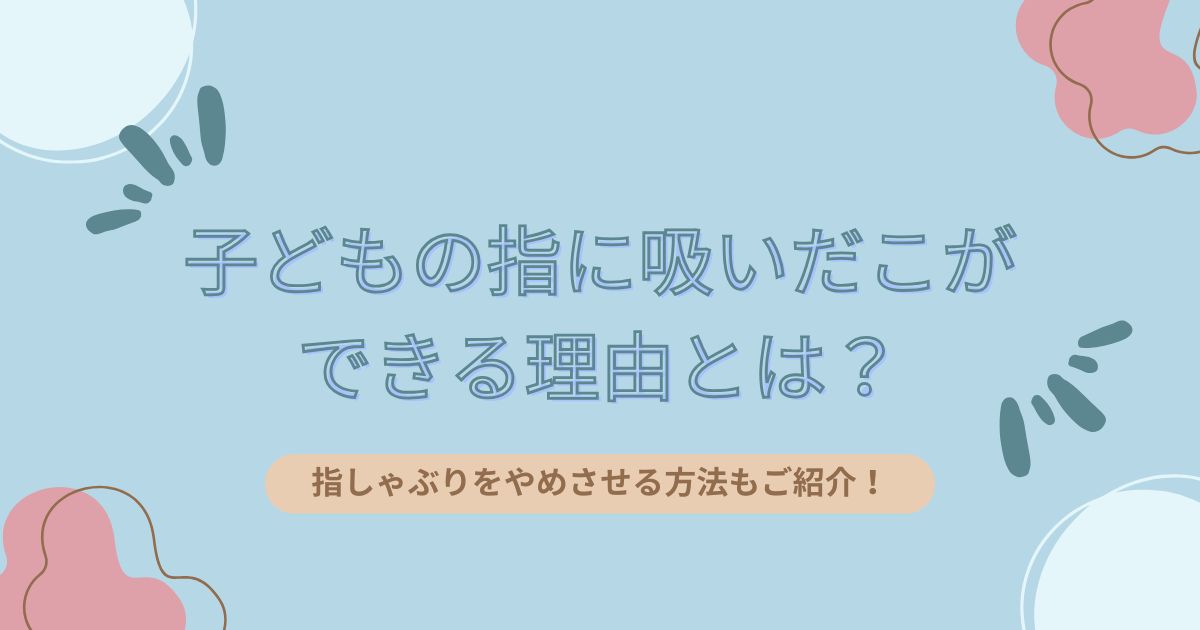
-65-150x150.jpg)

-120x68.jpg)