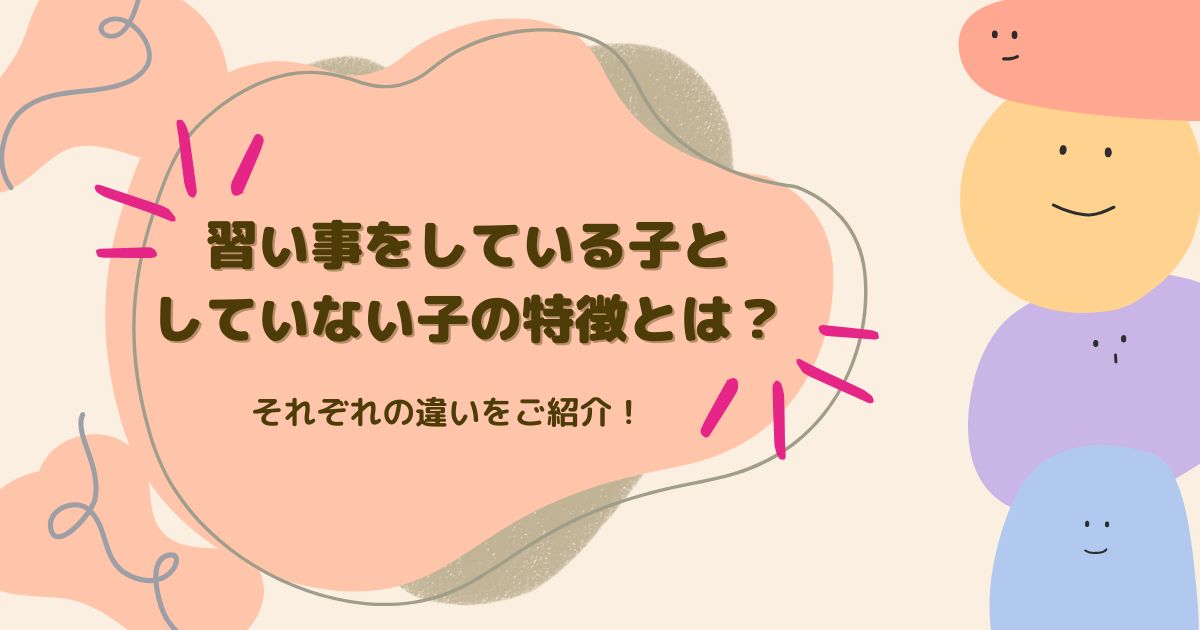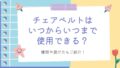子どもの習い事について迷っているママさんやパパさんで、「習い事をしている子としていない子で何か違いはあるの?」と気になっている方もおられるのではないでしょうか。大切なのは、それぞれの特徴を理解し、無理のない範囲で最善の方法をみつけてあげることです。
本記事では、習い事をしている子としていない子の特徴や違いについて解説します。また、習い事をするメリット・デメリットや習い事を選ぶときに意識したいポイントについてもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
習い事をしている子どもの特徴とは?

まず、習い事をしている子どもの特徴についてご紹介します。
- 時間の管理が上手になる
- 新しいことへの挑戦に前向きになる
- 社会性や協調性が育まれる
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
時間の管理が上手になる
習い事をしている子どもは、自然と時間を意識する習慣が身につきやすいです。「〇時にレッスンがあるから準備をしよう」「終わったらおやつの時間」など、日常生活のなかで予定を立てる力が育まれます。
とくに、幼児期は生活リズムが乱れがちですが、習い事があることで適度な区切りが生まれ、朝起きる時間や寝る時間も安定しやすくなります。小学校入学後の学校生活にもスムーズに適応できる力を養えるため、早いうちから時間管理を意識できる点が大きなメリットです。
新しいことへの挑戦に前向きになる
習い事を通じて、子どもは「できない」から「できた」への喜びを何度も経験します。この積み重ねが、未知のことにも恐れず挑戦する心を育てます。
たとえば、ピアノや水泳、体操など、最初は難しく感じたことでも、努力して乗り越えられた経験は貴重な体験です。幼児期に挑戦する楽しさを知ると、小学校以降の学習や人間関係にも前向きに取り組めるようになります。親が「がんばったね」としっかり認めることで、より意欲的な姿勢が引き出されます。
社会性や協調性が育まれる
習い事では、先生や友達との関わりを通して社会性を自然に学んでいきます。たとえば「順番を守る」「相手の話を聞く」「協力して一緒に活動する」など、家庭だけでは経験しにくい場面が豊富です。
とくに、幼児期は自己中心的になりやすい時期ですが、習い事を通じて他者を意識する行動が身につき、集団生活に必要な土台が育ちます。小学校入学後の集団生活にもスムーズに馴染みやすくなるため、早いうちからの経験が大きな財産になります。
習い事をしていない子どもの特徴とは?

次に、習い事をしていない子どもの特徴についてご紹介します。
- 自由な時間を多く持てる
- 自分で遊びを見つける力が育まれる
- ストレスを感じにくい傾向がある
それぞれの特徴について詳しくみていきましょう。
自由な時間を多く持てる
習い事をしていない子どもは、1日のなかで自由に使える時間が豊富にあります。この時間は、好きな遊びをじっくり深めたり、自分なりに興味を広げたりする大切な時間です。
とくに、幼児期は空想遊びやごっこ遊びが脳の発達に良いといわれています。予定に追われない生活はストレスを感じにくいため、のびのび育つための大切な土台にもなります。
自分で遊びを見つける力が育まれる
習い事に頼らずに過ごすことで、子どもは「今日は何をして遊ぼうかな?」と自ら考える機会が増えます。公園での遊び、絵本を読んでのごっこ遊び、段ボールを使った工作など、自分で遊びを作り出す力は、柔軟な思考力を育てるのに非常に効果的です。
幼児期に「自分で生み出す」経験を重ねることで、意欲や想像力がどんどん伸びていきます。
ストレスを感じにくい傾向がある
習い事がない子どもは、毎日のスケジュールに追われる場面が少なく、自分のペースで生活できます。とくに、幼児期はまだ体力も精神力も発展途上です。決まった時間に決まった場所へ行く負担がないため、無理なく自分らしく過ごせる環境がストレスの少ない成長につながります。
もちろん、何もしない時間が続くと退屈になったりする場合もありますが、それもまた「何をして過ごすかを考える力」を育む大切な機会になります。
習い事をしている子としていない子に見られる違い

次に、習い事をしている子としていない子に見られる違いについて解説します。
- 生活リズムや時間の使い方
- 自己肯定感や達成感
- 友達との関わり方
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
生活リズムや時間の使い方
習い事をしている子は、決まった時間に行動する習慣が身につきやすいのが特徴です。一方で、習い事をしていない子は、日によって過ごし方が柔軟で、自由な時間を持てるという利点があります。
どちらにも良い面があり、子どもの性格や家庭の方針によって、どちらが合っているかは異なります。大切なのは「規則正しく過ごせているか」「無理をしていないか」を親が見守ることです。幼児期の生活リズムは、その後の成長にも大きな影響を与えます。
自己肯定感や達成感
習い事をしている子は、「できるようになった」という達成感を積み重ねることで自己肯定感を高めやすくなります。たとえば、逆上がりができた、水泳でバタ足が上手になった、など目に見える成長がわかりやすいためです。
一方、習い事をしていない子も、日々の遊びや生活のなかで「自分で考えてできた」という喜びを経験できます。どちらにせよ、子どもが「自分はやれる」という感覚を持てるよう、親が小さな成功を認めてあげることが何より大切です。
友達との関わり方
習い事に通っている子は、家庭外の友達と接する機会が自然と増えます。同じ目標に向かって一緒にがんばる経験は、協調性や助け合いの心を育てるのにとても効果的です。
一方で、習い事をしていない子は、近所の子どもや保育園・幼稚園のお友達との自由な遊びを通じて、人との関係を築きます。どちらの関わり方にも良さがあり、無理に交友関係を広げる必要はありません。子どもが安心できるペースで、少しずつ世界を広げていくサポートを意識しましょう。
習い事をするメリット・デメリット
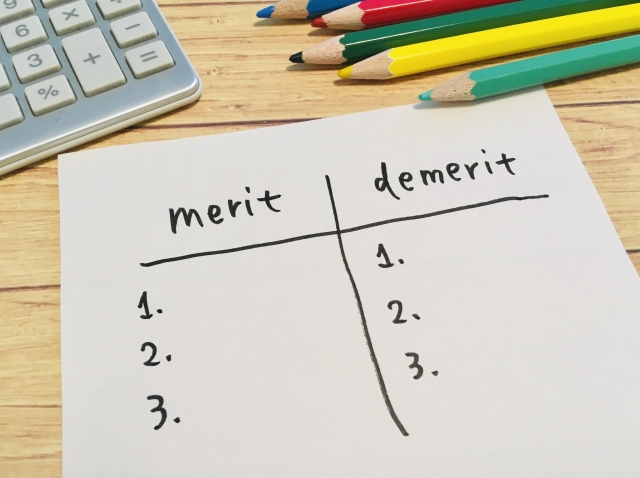
次に、習い事をするメリット・デメリットについてご紹介します。
- メリット
- デメリット
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
メリット
習い事には、子どもの成長を多方面から支える魅力があります。興味のある分野に取り組むことで集中力や探究心が育ち、学ぶ楽しさを自然に感じられるようになります。
また、集団のなかで行動することで思いやりやルール意識も身につき、社会性の基盤づくりが可能です。ただし、無理に続けさせるのではなく、子どもが楽しんで取り組めるかどうかを常に見守り、無理のない範囲で進めることが何よりも大切です。
デメリット
習い事には多くのメリットがある一方で、注意すべき点も存在します。とくに幼児期は、自由に過ごす時間のなかでしか得られない発見や体験があります。予定が詰まりすぎると、自分で遊びを考える力やリラックスする時間が不足してしまいかねません。
また、子どもが本当に楽しめていない場合には、やる気の低下や不安につながる場合もあります。習い事はあくまで選択肢のひとつと捉えて、子どもの様子を丁寧に見ながら、無理のない範囲で取り入れるようにしましょう。
習い事を選ぶときに意識したいポイント

次に、習い事を選ぶときに意識したいポイントについて解説します。
- 子どもの興味や性格に合っているか
- 無理なく続けられるか
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
子どもの興味や性格に合っているか
習い事をはじめる際には、子どもが「やってみたい」と感じる気持ちを尊重することが大切です。親の意向だけで決めてしまうと、子どもにとって負担になったり、途中で意欲を失ったりする可能性があります。
その子の性格や得意なこと、日頃の関心を丁寧に観察しながら、無理なく楽しめる選択を心がけましょう。体験の場を活用して、実際にやってみたときの反応を確かめることも、継続しやすい習い事を見つけるポイントになります。
なお、子どもに人気の習い事については、こちらの記事でご紹介しています。
関連記事:子どもに人気の習い事ランキング|習い事のメリット・デメリットや注意点もご紹介します!
無理なく続けられるか
習い事をはじめる際は、通う距離や時間帯、月謝なども大切なポイントです。幼児期は疲れやすいため、移動時間が長いと習い事そのものが負担になってしまう場合があります。
レッスンの曜日や時間が、家庭の生活リズムに無理なく組み込めるかをしっかりチェックしておきましょう。また、月謝や道具代など、経済的にも続けられるかを事前に確認しておくと安心です。習い事を「続けられる楽しみ」に変えるために、環境づくりも大切な要素の1つです。
習い事をはじめるのに向いているタイミング

子どもが何かに興味を示したときが、習い事を始める絶好のタイミングです。たとえば、「ピアノを弾いてみたい」「水泳に挑戦したい」と口にするなら、前向きな気持ちが芽生えている証拠です。
無理に早くはじめさせる必要はなく、子ども自身が「やりたい!」と感じたときのほうが、長続きしやすく、成長にもつながります。興味を引き出すために、体験レッスンや見学に行くなど、自然な形で触れさせてみるのもおすすめです。
なお、習い事を何歳から始めたらいいのか気になる方は、こちらの記事も確認してみてください。
関連記事:習い事は何歳から始めたらいい?おすすめの習い事や選ぶ際のポイントをご紹介します! | こそだて+
習い事をしていない子どもに必要なサポート

最後に、習い事をしていない子どもに必要なサポートについてご紹介します。
- 日常生活での経験の幅を広げる
- 自己表現の機会をつくる
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
日常生活での経験の幅を広げる
習い事をしていない子どもでも、日常生活のなかでたくさんの経験を積めます。たとえば、公園で虫を観察したり、親子で料理をしたり、季節ごとのイベントに参加したりすることも立派な学びです。
幼児期はとくに「五感」を使った体験が心に残りやすいため、難しいことを教えるよりも、親子で一緒に楽しみながら世界を広げることが大切です。どんな小さな体験も、子どもにとっては大きな成長の種になります。
自己表現の機会をつくる
習い事をしていない場合でも、自分の考えや気持ちを表現する場を持たせることが大切です。たとえば、お絵描き、工作、簡単な劇ごっこなど、家庭のなかでも自己表現の機会を作ることは可能です。
親が「すごいね」「どうやって思いついたの?」と声をかけるだけで、子どもは自信を持ちやすくなります。自由な発想を受け止めることで、自己肯定感を育てる土台ができ、将来的な自己表現力にもつながります。
まとめ

本記事では、習い事をしている子としていない子の特徴や違い、習い事をするメリット・デメリット、習い事を選ぶときに意識したいポイントについてご紹介しました。
習い事をしている子としていない子、それぞれに違った成長のかたちがあります。どちらが正解というわけではなく、大切なのは子ども自身がのびのびと過ごせているかどうかです。
習い事を通じて社会性や挑戦心を育む子もいれば、自由な遊びから創造力を伸ばす子もいます。親の思いだけで決めず、子どもの気持ちや家庭のリズムに合わせた選択をしていくことが、無理のない成長につながります。