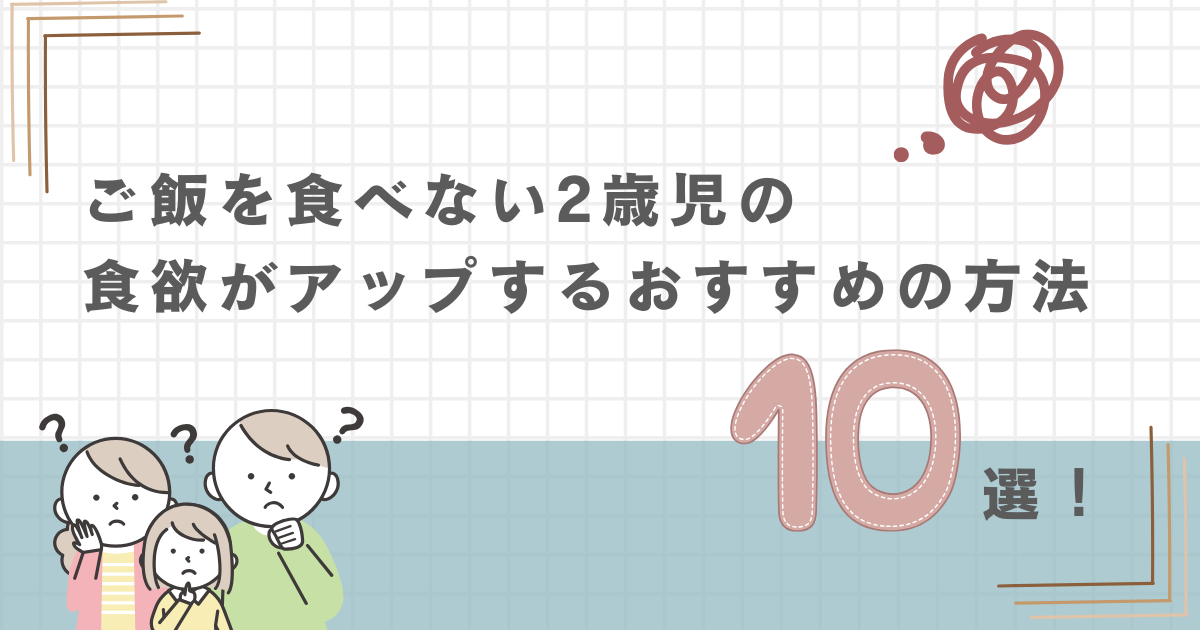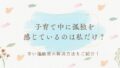子どもがご飯を食べてくれなかったり、食べムラがあったりして悩まれている方も多いのではないでしょうか。色々な工夫を取り入れてみるものの、あまり効果がないというケースも珍しくありません。
このような悩みを抱えている方は、子どもがご飯を食べない理由から理解していきましょう。それから、食事の方法や環境などを工夫してみると、食事の楽しさを感じてもらいやすくなります。
2歳児がごはんを食べない主な理由は5つ

2歳児がごはんを食べない場合、親としては焦ってしまいますよね。子どもの健康はもちろん、ご飯の片付けが進まないのも困ります。では、子どもがご飯を食べない理由には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、主な理由をご紹介します。
- 好きなものや嫌いなものがわかってきている
- 噛みにくさや飲み込みにくさがある
- 食事以外に興味や関心がわいている
- なんでも「イヤ!」と言いたがる
- お菓子を食べ過ぎている
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.好きなものや嫌いなものがわかってきている
2歳児になると、食事に対するこだわりが強くなり、それまで問題なく食べていたものを突然拒否する場合があります。特定の食材や味だけでなく、見た目や食器の種類、食べる環境によっても食欲に影響が出やすい時期です。
たとえば、いつもと違うお皿を使っただけで食べなくなったり、お気に入りの席でないと嫌がったりする場合も少なくありません。こうした変化に対しては、無理に食べさせようとせず、子どもの気持ちに寄り添いながら柔軟に対応するようにしましょう。
2.噛みにくさや飲み込みにくさがある
2歳児の食事は、大人と同じようなメニューに移行しますが、食べやすさに工夫が必要です。咀嚼力や飲み込む力には個人差があり、硬い肉や繊維質の野菜、ぱさぱさした魚などは食べにくい場合があります。
咀嚼して疲れたり、飲み込みづらさを感じたりすると、食欲が低下してしまいかねません。このため、食材を細かく刻んだり、少しとろみをつけたりするなど、子どもが無理なく食べられる工夫が大切です。食事が楽しい時間になるよう、子どもの発達に合わせた調理を心がけましょう。
3.食事以外に興味や関心がわいている
2歳児は好奇心が旺盛で、食事中でも周囲の出来事に注意が向きがちです。食べ物の形や感触を確かめるのに夢中になったり、部屋の中の物に気を取られたりして、なかなか食べ進めない場合もあります。
おもちゃやテレビなどの視覚的な刺激があると、さらに集中力が途切れやすくなります。このため、食事中は余計な刺激を減らして、落ち着いてしっかり食べられる環境作りや工夫をしてみましょう。
4.なんでも「イヤ!」と言いたがる
2歳頃になると、自分の意思を強く持つようになり、何かを指示されると反発したくなる場面が増えます。食事の場面でも「これを食べて」と言われると、理由もなく「いや!」と拒否する場合があります。
はじめて見る食材や、気分が乗らない食べ物には、警戒心を持って手をつけようとしないケースも珍しくありません。これは自立心の芽生えの一環であり、成長の証です。
無理に食べさせるのではなく、一緒に食べたり、親が食べる姿を見せたりして、子ども自身が興味を持てるような工夫が大切です。
なお、イヤイヤ期が早い子どもの特徴については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:イヤイヤ期が早い子どもの特徴とは?接する際のポイントや注意点を詳しくご紹介!
5.お菓子を食べ過ぎている
2歳児が食事をあまり食べない原因の1つとして、空腹でない場合があげられます。おやつを食べ過ぎたり、食事の直前に何かを口にしてしまったりすると、十分な食欲が湧かなくなるケースも少なくありません。
また、日中の活動量が少ないと、エネルギーの消費が少なくなり、お腹が空きにくくなります。食事をしっかりと食べてもらうためには、おやつの量や時間を調整して、適度に体を動かす機会を作ることが大切です。食事とおやつのバランスを意識しながら、無理なく食欲を引き出していきましょう。
ご飯を食べない2歳児の食欲がアップするおすすめの方法10選

ここからは、食欲がアップするおすすめの方法10選をご紹介します。試しやすい方法ばかりのため、子どもがご飯を食べずに困っている方は、ぜひ試してみてください。
1.小さく切ったりとろみをつけたりする
食事をなかなか食べない2歳児には、食材の形や調理方法を工夫してみましょう。たとえば、噛みにくい肉や葉物野菜は細かく刻んだり、やわらかく煮込んだりすると食べやすくなります。
魚のパサつきが気になる場合は、あんをかけてとろみをつけると飲み込みやすくなります。また、自分で食べることに興味を持つ時期でもあるため、一口サイズのおにぎりやスティック状の野菜を用意するのも効果的です。
2.間食の量を少なくしてみる
おやつの時間と食事の間隔が短いと、食事の時間になってもお腹が空かず、食べる量が減ってしまう場合があります。間食は、成長に必要な栄養を補う目的で取り入れるものであるため、食事に影響を与えないようにしましょう。
おやつの時間は、食事の1〜2時間前を目安にして、量も適量に調整するのがおすすめです。また、おやつの内容も栄養バランスを考えたものにすると、次の食事にもつながりやすくなります。食事とのバランスを意識しながら、上手に取り入れていきましょう。
なお、おやつの適切な量やタイミング、選び方ついては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:2歳の子どもにおやつが必要な理由とは?食べさせ方や市販のおやつ7選をご紹介!
3.食べものになりきってみる
子どもがなかなか食べてくれないときは、食材に声を当ててみるのも1つの方法です。たとえば、「ブロッコリーさんが『〇〇ちゃんに食べてもらいたいな~』って言ってるよ!」と楽しく声をかけると、興味を持ってくれる場合があります。
また、乗り物が好きな子には「スプーンバスが〇〇ちゃんのお口に到着しま~す!」といった実況風の言葉がけも効果的です。親にとっては少し大変かもしれませんが、遊び感覚で食事を楽しめるため、食べる意欲を引き出しやすくなります。
4.食器を好きなキャラクターに変える
食事に興味を持たせる工夫として、子どもの好きなキャラクターや色の食器を使うのも効果的です。お気に入りのデザインだと嬉しくなり、自分から進んで食べようとする場合もあります。
また、食器の底にイラストが描かれている場合、「全部食べると〇〇が見えるよ!」と声をかけると、楽しみながら食事を進めるきっかけになります。しかし、夢中になって早食いしてしまわないよう、「よく噛んでね」と優しく声をかけながら、食べるペースを見守りましょう。
5.お皿に載せる量を少なくする
食べることにあまり積極的でない子は、最初からたくさん盛られていると「食べきれない」と感じてしまい、食欲が落ちる場合があります。このため、まずは少量を盛り、食べ終わったらおかわりできるようにすると、負担が減り、自然と食べる量が増える可能性があります。
「完食できた!」という達成感も得られるため、食事への前向きな気持ちにつながりやすいです。子どものペースに合わせた量を意識しながら、無理なく食事を楽しめる工夫をしてみてください。
6.子どもの好きなお人形と一緒に食べる
食事の時間を楽しくする工夫として、お気に入りのぬいぐるみや人形を一緒に座らせるのも効果的です。「〇〇ちゃんと一緒に食べよう!」と声をかけたり、人形に食べさせるふりをしたりすると、子どもが興味を持ちやすくなります。
また、「ぬいぐるみさんも食べたいって言ってるよ」と遊びの要素を加えると、自然と食事が進む場合もあります。同年代の子と食べる機会が少ない場合でも、こうした工夫で楽しい食卓の雰囲気が作れるため、食事への意欲を高めるきっかけにもなりやすいです。
7.周りのものが視界に入りにくい位置に座る
食事に集中しにくい子は、座る位置を工夫するだけで改善できる場合があります。食卓の周りにおもちゃやテレビが見えると、気が散って遊び食べにつながりやすいです。
このため、なるべく視界に余計なものが入らないよう、子どもの背後におもちゃやテレビを配置したり、テレビを消したりして食事に集中しやすい環境を整えるのがポイントです。視覚的な刺激が減ると、ご飯に意識が向きやすくなり、スムーズに食べ進められます。
8.お腹が空いた状態でご飯の時間にする
食事やおやつを決まった時間に食べる習慣がつくと、「この時間はご飯」と理解しやすくなり、自然とお腹が空くリズムが整いやすくなります。仕事などの都合で時間の調整が難しい場合は、食事とおやつの内容を工夫するのも1つの方法です。
たとえば、おやつに主食を取り入れ、食事の際は野菜中心のメニューにすると、バランスよく栄養を摂取できます。子どものペースに合わせた調整を意識しながら、無理なく食事を進めていきましょう。
9.大人が率先して楽しそうに食べる
子どもが食事を楽しめるようになるためには、大人が率先して食事の時間を楽しいものにする工夫が大切です。親がおいしそうに食べる姿を見せると、「ご飯は楽しいもの」と子どもが自然に感じるようになります。
見慣れない食材に抵抗を示したときは、無理に食べさせようとせず、大人が美味しそうに食べる様子を見せると興味を引きやすくなります。また、食事中にこぼしたり、残してしまったりしても、食事に対して前向きな気持ちを育てるために、怒らずに「食べられたね」と褒めてあげましょう。
10.ご飯に関する絵本で食べものへの関心を高める
絵本に登場する食材が食卓に並ぶと、「絵本に出てきたやつだ!」と興味を持ちやすくなります。また、「お肉を食べると力が出るよ」「お野菜を食べると元気になれるよ」といった簡単な言葉で、食べることの大切さを伝えるのもおすすめです。
難しい説明は理解できなくても、楽しく学びながら食事の時間を迎えると、自ら食べてみようという気持ちを育てられます。
ご飯を食べない2歳児に向けたNGな行動は3つ

最後に、ご飯を食べない子どもに対して避けるべき行動をご紹介します。手間暇をかけて作った料理が食器にそのまま残っていると、悲しさや苛立ちがわいてくるかも知れません。しかし、感情的になるのは逆効果のため、以下の行動には注意しましょう。
脅して食べさせる
「食べないと〇〇が来るよ」「食べないと〇〇できないよ」と脅して食べさせる方法は、一時的には効果がありますが、子どもにとって食事の時間が怖いものになってしまう可能性があります。食事は本来、楽しく美味しく味わうものです。
無理に食べさせるのではなく、「これを食べると元気になるよ」「おいしいね」とポジティブな声かけをすると、自然と食事に対するよいイメージが育ちます。子どもが食事の時間を楽しめるよう、安心して食べられる雰囲気作りを心がけましょう。
無理に口に入れて食べさせる
子どもがご飯を食べないからといって、無理に口に入れたり、強制的に食べさせたりするのは絶対に避けましょう。こうした行為は子どもにとって大きなストレスとなり、食事に対する苦手意識を強めてしまいかねません。
また、無理に食べさせると窒息のリスクも高まり、非常に危険です。食事について不安がある場合は、専門機関や医師に相談して、無理のない方法で食事の時間を楽しいものにできるよう工夫していきましょう。
友達や兄弟と比べる
子どもが食事をする際、「〇〇ちゃんは食べられたのに」などの言葉は、子どもが自分を否定されたように感じ、食事への意欲を下げてしまう場合があります。一方で、「〇〇ちゃんも少し食べてみる?」と優しく促すような声かけは、無理なく興味を持たせるきっかけになる可能性があります。
このため、子ども自身のペースを大切にして、小さな一歩でも「すごいね」「がんばったね」と褒めてあげることが大切です。
まとめ

本記事では、2歳児がごはんを食べない主な理由や食欲がアップするおすすめの方法、ご飯を食べない2歳児に向けたNGな行動をご紹介しました。
2歳児になると、食事に対するこだわりが強くなり、何かを指示されると反発したくなるケースが増加する傾向にあります。このため、それまで問題なく食べていたものを突然拒否する場合があります。
さらに、噛みにくさや飲み込みにくさ、食事以外への興味によって食事が中断するケースも珍しくありません。このため、食材を小さく切ったりとろみ付けをしたりして、食べやすくする工夫や食事に集中できる環境を用意することが大切です。
また、親が食べものになりきってみたり、楽しそうに食べてみたりといった雰囲気作りも大切です。子どもと親が無理なく出来る方法を見つけてみましょう。
一方、脅して無理に口に入れたり、きょうだいや友達と比べたりするのは避けてください。こうした行為は子どもにとって大きなストレスとなり、食事に対する苦手意識を強めてしまいかねません。
食事は、子どもの健やかな成長には欠かせない大切な時間です。楽しい食事の時間を家族で過ごせるように、子どもへの接し方を工夫してみてください。